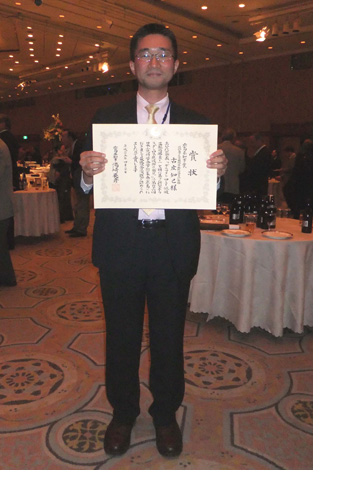医学部附属病院遺伝子診療部の古庄知己准教授が第116回日本小児科学会学術集会で最優秀演題賞である広島県知事賞を受賞しました。
2013年4月19日(金)~21日(日)に広島市で開催された第116回日本小児科学会学術集会において、医学部附属病院遺伝子診療部准教授の古庄知己さんが、最優秀演題賞である広島県知事賞を受賞しました。小児科関連最大規模の学術集会であり、全1055演題のなかからの受賞という快挙でした。
受賞対象となった発表演題は「デルマタン4-O-硫酸基転移酵素1欠損による新型エーラスダンロス症候群の発見」です。古庄さんは、10年前に顔貌上の特徴、先天性多発関節拘縮、そして進行性の全身結合組織脆弱性を呈する1人の患者さんに出会いました。過去の症候群に合致しない特異な症状であったことから新規症候群ではないかと推測、その後症状の酷似した複数の患者さんを見いだし、「エーラスダンロス症候群、古庄型」と提唱しました(Kosho et al., 2005; Kosho et al., 2010)。並行して、国内基礎研究者との共同研究により、原因遺伝子がデルマタン4-O-硫酸基転移酵素1(D4ST1)をコードするCHST14であることをつきとめました(Miyake et al., 2010)。D4ST1は、コンドロイチン硫酸(CS)とともに、プロテオグリカンのグリコサミノグリカン(GAG)鎖を構成するデルマタン硫酸(DS)の生合成に必須の酵素です。本酵素の欠損により、コラーゲン細繊維をきつく束ねるのに重要な役割を果たしているデコリンというプロテオグリカンのGAG鎖が、健常人であればほぼDSであるのが、患者さんではすべてCSに置き換わっていました。これによりコラーゲン細繊維がうまく束ねられなくなった結果、全身の進行性結合組織脆弱性を生じることがわかりました(Miyake et al., 2010)。
本症候群の存在には、世界の3チームが独立に気づいていました。古庄さんらは原因遺伝子の発見では2番目でしたが、その後、新たな患者さんを見いだすとともに、3チームが報告した過去の全患者さんの臨床症状を詳細に分析し、これらの患者さんは同一の症候群であると結論づけました(Shimizu et al., 2011)。そして、「デルマタン4-O-硫酸基転移酵素1欠損に基づくエーラスダンロス症候群(D4ST1-deficient EDS;DDEDS)」と命名しました(Kosho et al., 2011)。
本症候群は現在までに世界で26人が論文報告され、さらに国内外で新たな患者さんが続々と見つかっており、比較的頻度の高い疾患ではないかと考えられています。また、デルマタン硫酸生合成経路において初めて見いだされた異常症であり、ヒトを含めた生物におけるデルマタン硫酸の意義を考察する上できわめて重要なモデルであると位置づけられています。日本人が、オリジナルな発想で新規疾患の発見そして疾患概念の確立に貢献することはきわめてまれです。古庄さんの発見は高く評価されて、2011年度日本人類遺伝学会奨励賞も受賞しています。古庄さんは、厚生労働省難治性疾患克服研究事業「デルマタン4-O-硫酸基転移酵素-1欠損に基づくエーラスダンロス症候群の病態解析および治療法の開発」の研究代表者として臨床的および基礎的研究を推進しています。学内では、医学部組織発生学講座、分子病理学講座、運動機能学講座、形成再建外科学講座、耳鼻咽喉科学講座などとの共同研究が、学外では、国立精神神経医療研究センター、北海道大学などとの共同研究が、軌道にのっており、iPS細胞やノックアウトマウスを用いたさらなる病態の解明、そして遺伝子治療など根治療法の開発が期待されます。
研究の詳細は信州医学誌(59号5巻、305-319ページ、2011年)にまとめられておりますので、ご参照下さい(http://s-igaku.umin.jp/DATA/59_05/59_05_02.pdf#search='デルマタン+古庄')
附属病院遺伝子診療部(http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/chair/PM/)