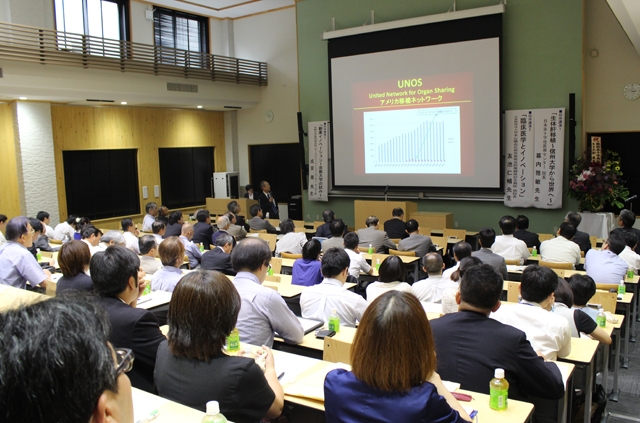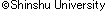医学部メディカル・ヘルスイノベーション講座キックオフ式典・講演会を開催
13年07月18日
平成25年7月13日、松本キャンパス医学部臨床棟にて、医学部の寄付講座メディカル・ヘルスイノベーション講座のキックオフ式典及び講演会を開催しました。
メディカル・ヘルスイノベーション講座では、主に医用・健康機器や機能性食品等の開発をめざし、イノベーション研究のプロジェクトをコーディネートできる人材を育成します。株式会社ブルボンと多摩川精機株式会社の2社による寄附講座で、本年4月に開設されました。
会場となった第一臨床講堂では、全国各地より参集した客員教授、関係者等、出席者110名の士気が高まる中、午後0時30分より式典が開始されました。
冒頭の挨拶で山沢清人学長は、「出口(開発の成果)への期待も大きいが、講座では基礎からシーズを作り上げる一貫した研究・教育を行う特徴があり、イノベーションの分野で活躍できる人材を育てるという重要な役割を担う。ここから他の講座も含めて、医学部全体が発展していくことを期待する」と関係者にエールを送りました。続いて中山淳副学部長(福嶋義光医学部長代理)、天野直二医学部附属病院長が挨拶し、ご来賓の方々の祝辞をいただきました。
厚生労働省大臣官房技術総括審議官の三浦公嗣氏は「医薬品や医療技術の開発は、健康長寿社会を実現し、経済を活性化させていく上で重要だが、その恩恵を実際に病気で困っている国民にあるいは世界の人々にどのように届けられるかが大切なポイント。この点でイノベーションは重要であり、この講座の取組みは大変大きな意義がある。できるだけの支援をしたい」と述べました。
また、独立行政法人科学技術振興機構執行役の黒木敏高氏は「我が国はイノベーションの創出を目指しており、イノベーション研究プロジェクトをコーディネートできる人材を強く求めている。本講座の人材の輩出に、大変期待している」と語りました。
続いて長野県商工労働部長太田寛氏の祝辞を、同ものづくり振興課長上原卓氏代読され、支援企業の株式会社ブルボン代表取締役社長吉田康氏と多摩川精機株式会社代表取締役社長萩本範文氏よりご挨拶をいただきました。
式典の締めくくりは、大橋俊夫医学部教授(平成26年度4月以降講座専任)が、講座の概要を説明し、30名の教員(医学部教員7名、特任教員5名、国内外の客員教授18名)について紹介し、出席した教員が一言ずつ挨拶しました。

講演会では、始めに、本間研一氏(北海道大学大学院名誉教授)、中畑龍俊氏(京都大学iPS細胞研究所副所長)、内山 聖氏(新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院長)3氏の客員教授が代表として挨拶し、本講座へ寄せる期待と夢を語りました。
招待講演の一つ目は「生体肝移植~信州大学から世界へ~」。移植の外科医として、また研究者として世界のトップランナーである幕内雅敏氏(日本赤十字社医療センター院長)が移植をめぐる最近の話題について語りました。
二つ目は「臨床医学とイノベーション」として、友池仁暢氏(公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院長)が、臨床研究からニーズの把握、新たなシーズが生まれイノベーションにつながっていく仕組みを語りました。三つ目は京都大学医学研究科メディカル・イノベーション・センター長の成宮周氏が、「創薬イノベーション~京都大学の試み~」と題し、大学のアイディアと企業のシーズをどうつないでいくのか、実践例をあげながら講演しました。
講演会の最後には、大橋教授が人材育成の一環として続けてきた海外派遣プログラムを履修した医学部5年生の窪田雅之さん、高野敬祐さん、橋本菜々子さんによる「カロリンスカ研究所実習報告」があり、緊張した面持ちで発表した学生たちに温かな拍手が送られました。
大橋教授は、本講座で米国流の知的財産活用の例示を自ら提示し、講座の3つの灯として、寄付支援企業とのWin-Winの関係、医学部教授らの矜持鍛錬と研究支援、学部・大学院学生の師を見出すプログラムを活用した人材の育成を挙げています。
20社以上の大学発ベンチャー創出に関わった大橋教授と、そうそうたる顔ぶれの教授陣に先見性のある支援企業2社がスクラムを組み、本講座は、医療イノベーションの夢に向かって確実な一歩を踏み出しました。