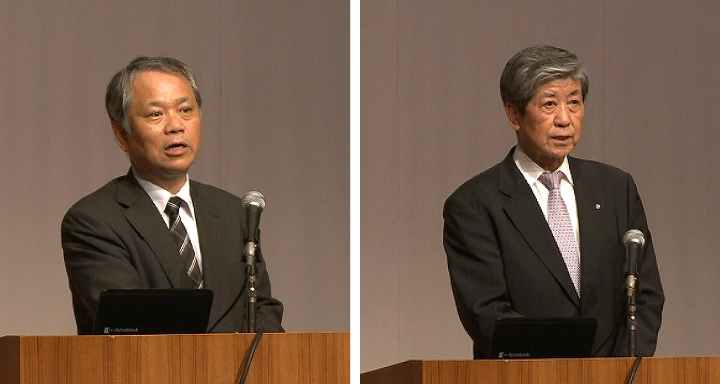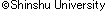長野県北部地震・栄村シンポジウム 「復旧・復興の現状と今後の課題―震災後7カ月を経過して―」 を開催
11年10月17日
3月12日の長野県北部地震から7カ月が経過し、栄村では大規模土石流の対策工事が行われ、国・県・村道の改修、橋梁・下水道工事が進み、農地の復旧事業も始まりました。さらにこれから村営住宅の建設や復興計画の作成が望まれる中で、信州大学中山間地域プロジェクトは10月16日(日)、農地の被災・集落調査の結果をもとに復旧・復興のあり方を考えるシンポジウムを開催、約100名の来場者に参加いただきました。
信州大学笹本副学長、栄村島田村長の主催者あいさつに続き、シンポジウムのねらい「栄村の復興の方向性・計画の重要性」として主催信州大学中山間地域プロジェクトの木村名誉教授から開催趣旨の説明があり、「農地に加え、住宅・倉庫・共同施設など多岐にわたる被害を縦割にならず、相互に関連付けた村の復興の方向をはっきりさせる夢・ビジョン・全体計画が必要」と語りました。続いて調査報告として農地災害調査から「農地災害調査から見た村の復興のあり方」として村の協力もいただき行った栄村小滝地区の被災調査について農学部内川助教の報告があり、村の復興のあり方を考える上で、住民・行政・コーディネーター・研究者の4者の連携が重要で、ひとつの復興モデルになると説明しました。
パネルディスカッションでは木村名誉教授が司会進行し、地元で復旧・復興に取り組まれている住民代表の方々と内川助教がパネラーに「栄村の復興の課題と今後の復興計画」と題して集落・村の復旧・復興のあり方について様々な意見交換を行い、これからの復興ビジョンや復興計画策定への有意義なシンポジウムとなりました。