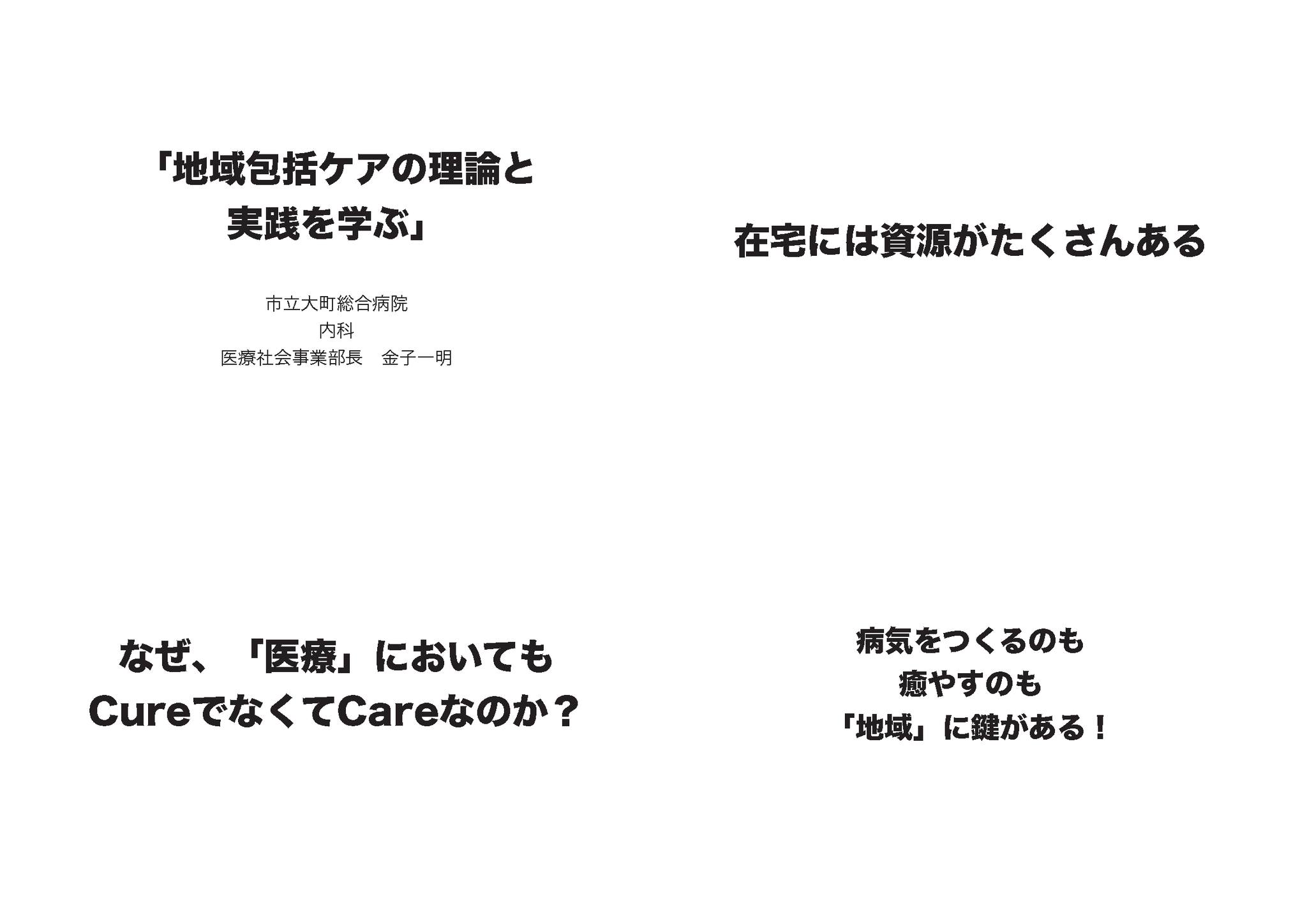2024年 第4回「地域医療」(医学科4年生)
2024.6.25更新

第4回目の「地域医療」の授業では、市立大町総合病院の金子一明先生にお話しいただきました。
以下が学生の感想の抜粋です。
※地域で医療を行うのではなく、地域を作る医療、のようなことをおっしゃられていたのが最も印象に残っています。どうしても、医師や医療の枠組みにこだわって、第三者の態度で関わってしまうことが多い気がしますし、実際私もしてしまう気がする、と気づくことができました。私は東京出身なので、誰しもが異なる場所から出勤してきて働くもの、という印象が強いです。その点、長野県、特に大町市などの過疎化している地域では、医療関係者がその地域で暮らしていたり、似たような地域に住んでいたりなど、地域の一員としての意識を持ちやすいように感じました。もちろん、住む場所など関係なく、地域の一人として何ができるのか考えれるようになることが理想なのだと思いますが。
※いいことも悪いことも含め、地域で支えるということはどういうことなのかを考えるきっかけとなりました。また、偽医者の映画のワンシーンを見て、家族などに介護されている末期の患者をどこまで処置をして助けるのか、難しい問題だと思いました。地域と関わり、人と関わっていく中で、病気の高齢者の介護の大変さや金銭面の苦労などを医師自身もより近くで知る状況でときには無理までして助けないという判断をすることもあるのかなと思います。ただ、やはり医師の仕事の大きな目的は命を助けることだと思うので、最後まで命をつなぐ努力はしたいと思うし、反対に患者さん本人や周りの支えている人も患者さんに対して心からまだ生きてほしいと思えるような社会的な制度がもっと整えば良いとも思いました。しかし、現実的にはむずかしいことだと思うので、将来自分が医師になって、その命をつなぎたいという理想的な思いと、そうはいかないという現実的な思いの狭間で悩むことも少なくなさそうだと感じました。
※在宅には資源が沢山あるという見方が新鮮でこれまで自分の視点に無かったものだったので、興味深くうかがえました。景色やひ孫、猫だったり住み慣れた家という環境そのものだったり、患者さんによって大事に思う資源は違いますが、それぞれが大切に思えるものが家にはあって、そこでCareを行うことは、高齢化社会を生きていく私たちにとって身近なテーマだと思います。慢性疾患に対応していくために、将来医師としてどのようなキャリアを形成していくか考えさせられることの多い時間でした。ありがとうございました。
※医学モデルと生活モデルの違いが大切だとおっしゃっていました。自分は地域枠の生徒なので将来「地域」で働く可能性も高く、特にこの生活モデルの重要性を忘れずにいたいと思いました。医学の勉強をしていく中で、どうしても視点や発想が医学モデルに偏りがちだと思います。しかし地域社会の構成員である医者として、患者さんの生活モデルや背景の「地域」、そういったことに視点を置き、患者さんの求める地域での生き方を支えられるようになりたいと思いました。
※現在日本では貧困化や高齢化、人口減少など多くの問題点があることについても触れていただきました。今回のお話は、遠い将来(実はそれほど遠くないかもしれませんが)日本全国で現在の地域医療の現状が広がっていく中で、地域包括ケアの重要性を先行して示しているという点でとても最先端の医療であるようにも感じます。そういった意味でも、地域包括ケアをはじめとした地域医療に対する理解を改めて深めていきたいと思いました。
※今回の授業を聞いていて、ふと、医療って自己目的化しているよなと感じた。本来医療は病を抱える患者を治し健康に生活できるように手助けすることを目的にしていたはずが、医学の発展により疾病の治療に重きが置かれるようになってきた歴史があるのだろうと思う。大学の医局や派閥間のいざこざなども患者をみていないなと思う。そのような点で、家庭医療は「人を診る」という魅力があると感じた。