2024年 第3回「地域医療」(医学科4年生)
2024.6. 5更新
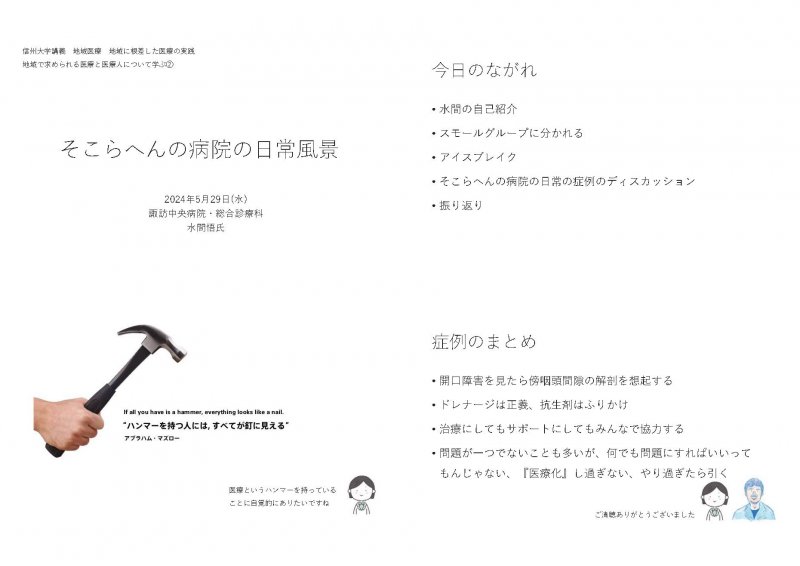
第3回目の「地域医療」の授業では、諏訪中央病院総合診療科の水間悟氏先生にお話しいただきました。
以下が学生の感想の抜粋です。
※症例の患者さんに対しできることとして、良かれと思ってたくさんの支援を提示しようとしました。しかし、支援を必要としない人もいるし、そもそも私が提示したものは患者さんというより医療者・介護者の負担を減らすことが主な目的だったのかもしれないと気付かされました。
※医師は患者さんとの間に病気を挟まないと患者さんに触ることができないという話が印象に残りました。病気を通して患者さんに関わっていくだけでなく、患者さんの周りの環境やその人がどうしたらその後生活しやすくなるかを考えて診療にあたる必要があると感じました。
※地方病院での実際の症例を一緒に考えながら追っていくことで、どこで困るのか、どのような背景があるのかなどを学ぶことができました。ところどころに挟まれるグループワークが非常に楽しく、水間先生のリアクションもとてもポジティブで答えやすかったです。
※アクティブラーニング形式の授業はとても興味深かった。最初のアイスブレイクもやったこともないもので楽しかった。医療体制が十分でない地域で、安易に信大病院などの大病院に送るのではなく、できる事をやることが大事だと学んだ。
※病院の中で医師が行っていることは、川の下流で人を救い上げていることと同じいとうお話は印象的でした。そのうえで、少しでも上流を見てみようとすると今回お話の中で出てきた症例の患者さんのように一つの主訴に対して他の背景が見えてくるものなのかなと思いました。そのような複合的な問題の中で医療が果たせることは実はそれほど多くなく、途中までは医療者としてそんな中でできることは何だろうと考えていたのですが、最後のお話を伺って、誰が何に困っているかをはき違えないという言葉に新鮮な気持ちを持ちました。何ができるかを考えてしまいがちですが、何を求めているのか、本当にそれを必要としているのか、についても考えることが大事だと気づきました。疾患がないと患者に触れられない職業だというお話も新鮮で楽しかったです。
※今回のご講義では、氷山の一角受診をする患者さんに対して本人が困っている症状への診断・対処をしつつ、生活背景や隠れた要素に目を向け考える一連の流れが、1人の患者さんの症例をじっくり追うことで多少なりともわかったように思います。水間先生や先輩の実際の診断や対応も自分達の考えのフィードバックになり、更にその後の経過からも予想通りとはいかない実臨床の難しさを実感しました。また、小規模病院である富士見高原病院の役割や限界について考えながらお話をお聞きしていましたが、今回の症例で深頚部膿瘍への治療に、信大の耳鼻科の医師が難しいと判断した方法ではなく、病院内の放射線科医師による違ったアプローチが行われたことに驚きました。専門科で細分化されている症例カンファよりも、小規模病院などでスタッフが一同に介してカンファレンスを行うことの意義や、それぞれで補って病院の医療を回していく姿勢を垣間見ることができました。今後の実習でより多くの患者さんに接して色々な経験をしていきたいです。
※今回の地域医療に関する講義は、とても有意義なものでした。特に、地域のリソースが限られた病院で、難しい患者さんにどのように対応するかを具体的に学べたことが大きな収穫でした。講義では、患者さんの頸部の奥深くにある膿をドレナージする場面があり、自分一人ではどうにもならないと感じたときに、素直に周囲に助けを求めたことで解決策が見つかるという経験をしました。この経験を通じて、難しい症例に対しては周囲に相談することの重要性を改めて実感しました。医療チームとしての連携の大切さを学べたことは、とても貴重でした。さらに、患者さんに対して医療知識を活かして様々なサービスを提供しようとすることが多い中で、患者さんにとって本当に必要なものと、おせっかいの境界を見極めることの大切さについても考えさせられました。この視点は新鮮で、患者さんのニーズに応えるために何が本当に必要なのかを常に考える重要性を感じました。今回の講義で学んだことを活かし、地域医療の現場でより良い医療を提供できるよう努力していきたいと思います。

