第3回『深志課題探究ゼミ2023』を開催しました。
2023.11.21更新
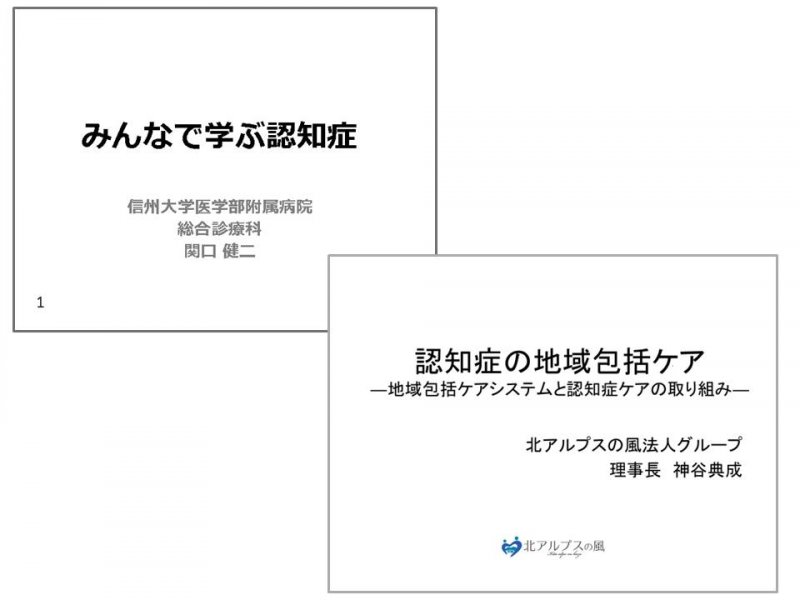
2023年11月18日(土)に松本深志高校1年生と信州大学医学科地域枠学生を対象とした第3回深志課題探究ゼミ・地域枠セミナー11月を開催しました。
今回のテーマは「認知症」で、信州大学医学部附属病院・市立大町総合病院総合診療科の関口健二先生には「みんなで学ぶ認知症」と題して認知症の医療について、北アルプスの風法人グループ理事長の神谷典成さんには「認知症の地域包括ケア」についてお話しいただきました。
以下が、参加者の感想抜粋です。
※認知症とは、他の風邪、感染症とは違って、治療というよりは、介護ということにフォーカスしなければいけないことがわかり、看護・介護するひとの大切さがわかりました。
※アルツハイマー型認知症に対する新薬は思ったよりも効果がない事、そしてこのようにこれから新たな事が医療の現場で出てくると思うが情報を鵜呑みにせず判断する事も医師に求められてる事を知る事ができました。
※ひと昔前は「認知症」という診断の必要がないほどおおらかな社会だったという言葉にはっとさせられました。今は認知症を病気として捉えてしまう世の中だけど、それを個性として捉えられる世の中になれば、認知症になっても、または認知症の人を支える側になっても、生きやすくなるのかなと考えました。
※認知症がもつ2つの側面、「疾患としての認知症」と「老いとしての(生活の中の)認知症」というお話がすごく印象に残っています。患者によって、重症度や症状は異なるわけで、疾患として医療が介入すべき場合と生活の工夫によりなんとかなる場合があることがよくわかりました。
※疾患として、老いとして(日常の中)の認知症それぞれの視点を示して頂いたことで、医師が全体の支援チームの中でどんな役割を担っているかを確認することができました。テレビの中の認知症は、徘徊が酷く言動も荒れ、生活が成り立たないというような印象を与えてきますが、実際には周囲の接し方により変わってくるということが更に当たり前の認識になるように、正しい情報を伝えていこうと思います。
※ジャンブルケアのお話が印象に残りました。特に、「注文を間違えるレストラン」の活動がとても興味深かったです。自分の役割があることでやりがいや充実感を感じるという言葉に納得しました。年齢や病気の有無にかかわらず、その人の居場所をつくることが大切だと感じました。
※介護現場、とくにグループホームでは、認知症の特徴に合わせた適切な介護が工夫して提供されていることがよくわかりました。認知症の患者・ご家族にとっての拠り所となるわけなので、今後ますます重要な役割を果たしていくのではないかと思います。
※認知症が必ずしも悪いことじゃないと言っていていい考え方だなっと思いました。
※医学生として学んでいるとどうしても患者さんを「特定の疾患を患っている人」としかみれなくなってしまうので介護職の方からの話は本当に大切にするべきだなと思った。特に若者は未来に向けた話、認知症の方は過去の話を意識するといいとありました。多分一生忘れない患者さんと話す時のポイントになると思います。
※介護の方法は間違えると高齢者の能力を奪ってしまうという言葉が心に残っています。私は現在介護が必要な祖母が二人、祖父が一人います。ご飯は作って食べれるだけでいいように、物は取ってあげるという関わり方をしてきてしまったので反省です。身体的にできないことを助け、できそうなことは一緒にやってみようと思います。また、祖父母が元気に長生きしていてほしいと未来のことを考えてしまいますが、過去に目を向けて祖父母のこれまでの生活からしっかり向き合って意思を尊重したいと思います。


