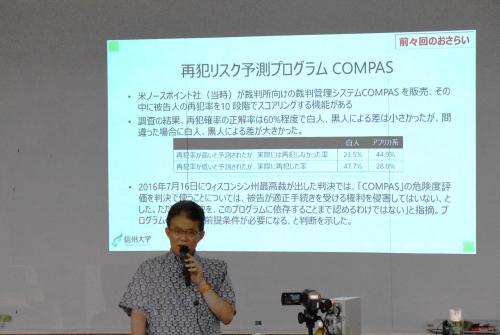TOPICS
トピックス
第13回ライフクリエイター入門演習が行われました。
ライフクリエイター入門演習
第13回 「AIと職業(1)」(2021年7月14日)
信州大学社会基盤研究所 特任教授 林憲一
第13回の講義は「AIと職業」と題し、科学技術の発展によってAIに代替される可能性が高いといわれている職業とそうでない職業とを紹介した上で、これからの社会で働く私たちに求められるのは、AIを使いこなしAIとともに生きる力であると強調しました。
1.職を失う人間
オックスフォード大学の2014年の研究報告によると、英国では今後の20年で35%の職種がAIによって置き換えられ、その可能性は低賃金の仕事の方が高いとされた。また、アメリカについては今後の10~20年ほどでIT化の影響で702の職種のうち、約半分が失われる可能性があり、書類作成や計算などの定型的な業務ではすでに機械化が始まり、会計士や税理士の需要が減っているとした。日本においても2015年に野村総合研究所が報告をまとめ、日本の被雇用者の49%が高い自動化リスクにさらされているとした。
いずれの場合においても、代替リスクが高いのは比較的定型的で単純な作業からなる事務職などの職種で、リスクが低いのはクリエイティブで大局的な難しい判断を求められる熟練管理職や法律サービス、人間と接することが好ましいとされる教育などの職種であった。
2.求められる「作る」力
時代の変化とともになくなる仕事もあれば、新しく増える仕事もある。例えば日本は過去に自動車立国という地位を確立してから、自動車関連の産業が広がって雇用が増えたといえる。これから日本が「AIを作る国」になるか、「AIを使うだけの国」になるかで日本の雇用情勢は大きく変わってくるであろう。
現状に目を向けると、インターネットで我々の生活は便利になった一方で、検索(Google)もスマホ(Apple)もソーシャルメディア(Facebook)もオンラインショッピング(AMAZON)もすべてアメリカの企業が作っているものである。
3.人間の付加価値
19世紀イギリスの産業革命時に、工場の機械化で失業を恐れた労働者たちが機械を破壊する運動(ラッダイト運動)が起きた。1990年代以降、IT技術の導入がもたらす技術的失業を懸念し、テクノロジーの発達・普及に対して反対する「ネオ・ラッダイト運動」が生まれている。
しかし、進むIT化により機械やロボットが行うサービスと人間が行うサービスとが分担され、人間によるサービスの付加価値はますます大きくなると考えられる。コミュニケーション力や人間力、教養は時代を超えて大切である。AIについて知識を深めると、自分の希望する職業の変化すべき方向が見えてくる。AIによる失職を恐れずAIを使いこなす職に就く準備こそがこれからの私たちに肝要である。