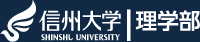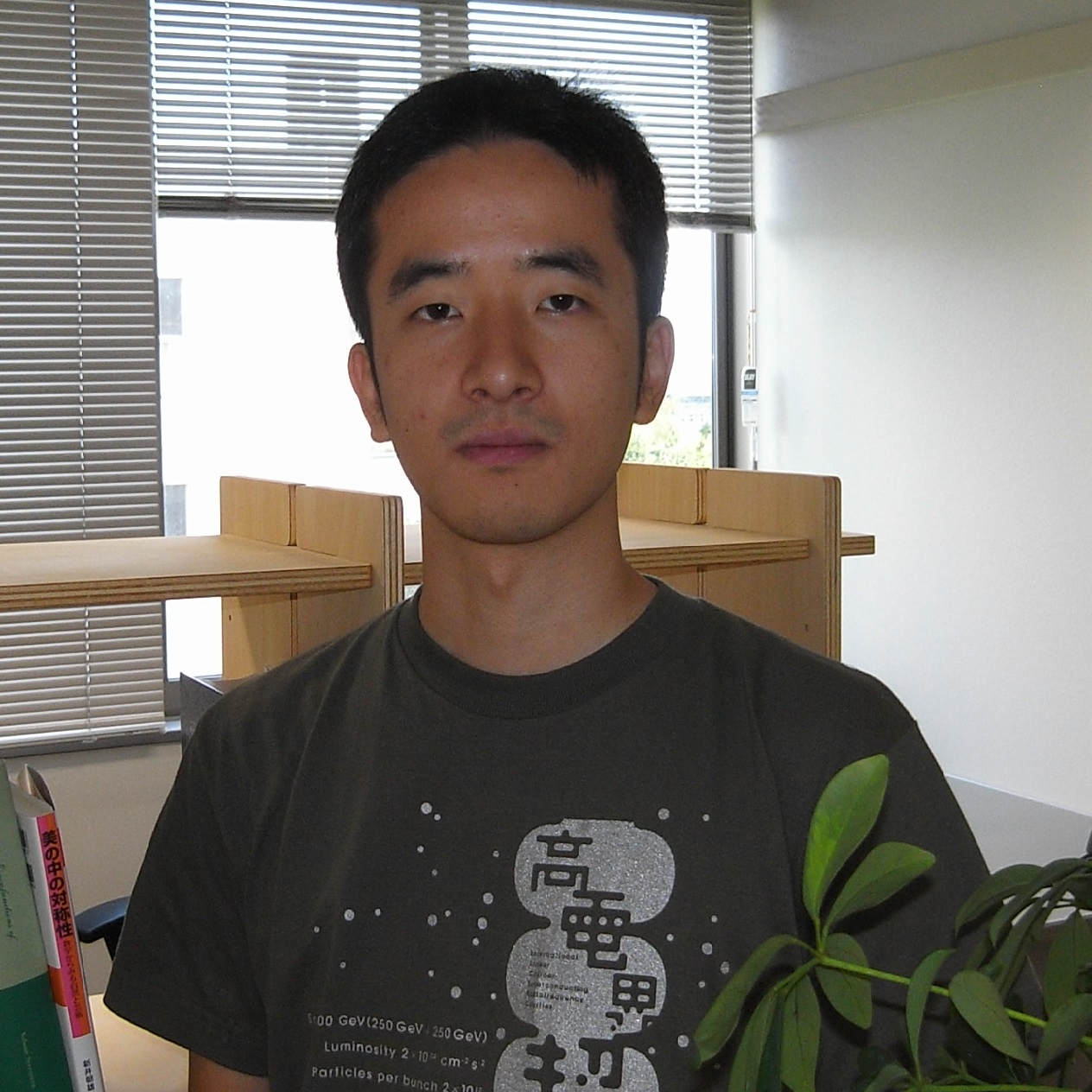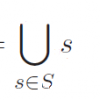現在の研究テーマ:数理物理と場の量子論
(1) なぜ身の回りにある物質は安定して存在するのか(2) なぜクォークは観測されないのか(3) なぜ熱は温かい物から冷たい物へ移動するのか,などの物理現象を基本的な数学モデルから厳密に解析してゆくのが数理物理です。問題(1) は20 世紀に大きな発展をして,広い条件の下で物質の安定性が示されましたが,まだ未解決の部分もあります。(2) はミレニアム懸賞問題の一つにもなっている有名な未解決問題です。(3) 一見すると簡単そうな問題ですが,実は熱現象の不可逆性(エントロピー増大則)を導くことは数理物理学上の大問題で,物理的に健全なモデルからこれを導くことにはまだ誰も成功していません。
私は"粒子系が量子場と相互作用する系"を研究しています。典型例は電子・陽子と量子電磁場の相互作用系です。水素原子を考えてみましょう。これは一つの電子と陽子からなる量子系です。電子は原子核に引っ張られて原子核の周りを回りますが,このとき時間変化しない安定な状態は存在するでしょうか?電磁相互作用を考えない場合,答えは簡単です。飛び飛びの値のエネルギー準位があり,それぞれに対応する定常状態が存在します。これがちょうど高校で習う殻K,L,M\(\cdots\)と軌道s,p,d\(\cdots\)に対応します。ところが電子は軌道を回るとき加速度運動をするので,振動数に応じて光を放出するはずです。そこでより正確に現象を記述しようと思うと電磁相互作用を考慮する必要が出てきます。この瞬間に問題は一気に難しくなります。加速度運動をする電子は無数の光子を生成または消滅し,生成した光は電子に複雑な相互作用を与えます。さらに電子は真空中では安定ではなく,光を纏ってエネルギーの低い状態へ遷移します。私たちが普段電子と思っているものはこの光の衣を纏った電子なのです。このとき光の衣の分だけ電子の質量が変化します。こうして何をもって電子と見なすのか,電子の意味は変わり,そもそも電子とは何であるのかを,考えなくてはならなくなります。電子と電磁場の相互作用の数学的形式を通して,電子の存在のあり方を必然的に考えさせられてしまうわけです。この衣は決して見えません。しかし観測はできなくても数学的な理性によってある意味で\感じる" ことができるのです。このことが数理物理のおもしろさの一つです。さて,このような複雑な状況ですが系はある定常状態をとることができるでしょうか?この問題については2000年頃に部分的に解決されて,最もエネルギーの低い状態は安定に存在し,励起状態にある電子は光を放出して基底状態に落ちることが示されました。でもまだ話は終わりません,最大の課題でもある散乱理論が残されています。これらの問題のいくつかは私達の世代で解決できるかもしれませんが,残りの大部分は次の世代(今の高校生の皆さん!)に残されることでしょう。
研究領域:関数解析・数理物理・量子論
量子力学の基礎方程式であるSchrödinger方程式 \[ i \frac{\partial}{\partial t}\Psi(t) = (-\Delta +V(x))\Psi, \quad \int |\Psi(x)|^2dx <\infty \] が発見されたのが1926年。それから直ちにJ. von Neumannによって直ちに本質が見抜かれて,量子力学はHilbert空間の作用素論として数学的な厳密性が与えられました(1932年)。量子力学が展開する舞台が無限次元の複素Hilbert空間です。これはベクトル空間で内積を持ちその内積から導かれる距離に関して完備な空間であると定義されます。たとえばベクトル空間 \[ \mathcal{H}=\left\{f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{C}\bigg| \int_{\mathbb{R}^3}|f(x)|^2<\infty\right\} \] は内積を \[ \langle \Psi, \Phi \rangle = \int_{\mathbb{R}^3}\overline{\Psi(x)}\Phi(x) dx \] としてHilbert空間となります。複素というのはベクトルに複素数倍を許す空間であるということです。単なる人工物と思われがちな虚数ですが量子力学では本質的な役割を果たします。量子力学では状態はHilbert空間の要素,物理量はHilbert空間の要素を他の要素へ移す線形変換(作用素)になります。たとえば\(H=-\Delta+V(x)\)はエネルギーに対応する作用素です。 方程式と状態には複素数が含まれますが,複素数が観測値に現れないために必要となるのが物理量の自己共役性です。この性質がないと確率解釈がうまくいきません。ただし作用素\(T\)の定義域を\(D(T)\)としたときその共役作用素\(T^*\): \[ D(T^*)= \{\Psi\in\mathcal{H}| |\langle \Psi, T \Phi \rangle| \leq C \| \Phi \| , \forall \Psi \in D(T) \} \\ \langle \Psi, T \Phi \rangle = \langle T^* \Psi , \Phi\rangle, \quad \forall \Psi\in D(T^*), \Phi\in D(T) \] が元の作用素と等しいとき-----つまり\(T=T^*\)-----作用素\(T\)は自己共役であるといいます。自己共役作用素と確率解釈で最も重要となるのがNeumannによって証明されたスペクトル定理です。
Neumannによって量子論の誕生後すぐに厳密化された量子力学の数学的理論ですが,本格的なSchrödinger作用素の解析が始まるのはNeumannの定式化のずっと後になってからで,1948年(出版は1951年)に加藤敏夫によって原子・分子に対するハミルトニアン \[ H=\sum_{j=1}^N (-\Delta_j+V(x_j))+\sum_{i \lt j}\frac{Ze^2}{|x_i-x_j|} \] の自己共役性が証明されSchrödinger作用素の数学的解析が始まりました。その後,数学者の興味を引いたSchrödinger作用素は解析は進み,1990年代にはCoulomb力を含む長距離相互作用を行う多体系に対して散乱理論の漸近完全性が証明されました。
一方,量子場の数学的理論は(はっきりしたことは私には分かりませんが)1950年代頃からA. Wightmanらによって始まったのだと思われます。当初の目標は場の理論の満たすべき公理系を提唱し,具体的に相対論的場の理論を数学的に構成することでした。相互作用を行わない場であれば具体的に量子場を構成することができます。そして非自明な相対論的場の理論の候補として\(\varphi^4\)モデルと呼ばれるスカラー場の研究が盛んに行われましたが,4次元時空では,逆に場の理論の自明性が証明されました。ただし相対論的共変性を諦めれば量子場の数学的理論をHilbert空間上に構成することができます。そのようなモデルで荷電粒子と電磁場の系のスペクトル解析を初めて行ったのは新井朝雄氏です。当初,量子場を解析する為の基本的な数学の手法はBogoliubov変換,有限体積近似,確率論的手法(汎関数積分法)などに限られていましたが,1996年頃にJ. Fröhlichらによる作用素論的繰り込み群の方法が開発されて共鳴極を数学的に捉えることが初めて可能になりました。共鳴極とは定常状態では無いけれども,準安定な状態に対応する(複素)エネルギーです。さらに2000年にはE. H. LiebらによってSchrödinger作用素に対して確立されていた,局在評価,指数減衰などが量子場の解析に応用され,大きな発展をしました。現在の未解決問題は量子場の系の散乱理論の構成です。これについては十分には満足のいく結果は得られていません。特に,相対論的な電子と光の散乱の散乱断面積を表すKlein-仁科の公式を数学的に導くという重要な問題が残っています。
最後に♪ 数理物理の魅力の一つに,自然が与えたモデルには美しい構造が隠されているという事があります。数理物理を学習することは,芸術作品を鑑賞することに似ているかもしれません。皆さんも信州の美しい自然の中で,美しい数学を学ぶことに貴重な時間を使ってみてはいかがでしょうか。