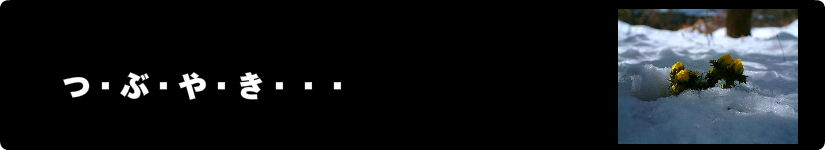—出会いで支えられた20年、有り難うございましたー
谷口 俊一郎 2016.3.31
信州大学にお世話になって早20年強が経ちました。この退職に当たっての記念誌は教室の方々の有り難い企画によるものです。一般の方々には無用のものかもしれませんが,もし,目を通して頂き何らかの参考になる点があれば幸いです。少なくとも私にとっては私の棺桶まで持っていきたい大切なものになると思います。
九州大学理学部では郷信広先生に生物物理学の理論面でのご指導を頂き、大学院理学研究科では指導教授である清水博先生に生体のエネルギー変換の生物物理学と生化学を学ぶ機会を与えて頂き、清水先生が東大へ異動なさった後の指導教授となって頂いた生化学者大村恒雄先生のご紹介で、医学部癌研(後に生体防御医学研究所)で馬場恒男教授の下、がんの実験病理学および化学療法の研究に携わりました。それから、助手になった後1982年から2年3ヶ月米国国立癌研(NIH内)で故角永武夫博士の下、癌の細胞生物学,特に細胞骨格の研究をさせて頂きました。馬場先生後任の勝木元也教授には発生工学技術を用いてノックアウトマウス作製をご指導頂きました。以上、まずはご指導頂いた各先生方に感謝の意を表したいと思います。
本誌には私の行って来た研究内容、論文リスト、ある意味での遺言となる研究活動を介した科学観、そしてご厚誼を頂いた方々の言葉が掲載されています。私自身の研究業績は自分の思い出となりますが、頂いた言葉は思い出以上に有り難いものです。人生では結婚式と葬式で2度位は褒め言葉を頂けると思いますが、それ以外の機会として本誌に頂いた言葉は私には大切な元気の糧になります。それらは全て温かく優しく中には面映いほど過分のお褒めや感謝の言葉もあり恐縮しています。しかし、煽てられた豚が木に登る感じで、素直に嬉しく温かい気分を与えられます。淋しくあるいは暗い気持ちになった時に繰り返し読むのではないかと思います。
赴任時は、新設教室だったので、場所も無く,何も無い状態からのスタートでした。しかし、実験室の設計を1、2週内で出来るなら旧動物実験施設をリフォームして提供可能だとのお話があり、徹夜状態で研究室内活動の理想的動線を考え設計図と取り組みました。これは、当時学部長であった發地雅夫先生のご高配でした。お陰様で着任1年後位には大変働き易い環境で研究生活をスタートし今日まで続けることができました。立ち上げ時は相良、竹岡両先生、第1号大学院生の増本君に苦労を掛けたと思います。しかし、それだけに面白くやり甲斐を共有できた時期だったとも思います。
第一に申し上げたいことは、在職期間、相良、板野そして肥田という優れた良き相棒准教授に恵まれたことです。そのお陰で、初期に目指した研究を進めることができ、困難も喜びも全てを楽しく愉快な思い出とすることができました。そして,彼らが私の在職中に各大学の教授に昇進してくれたことを心より喜んでいます。彼らの異動の度に、嬉しさと同時に自分の両腕を失う思いを味わいましたが・・。准教授のみならず、常に良き同僚に恵まれ,何とかやってくることができたことは誠に有難いことです。非常勤という不十分な雇用条件にも拘らず、厳しい台所状況の中でもきちんと管理運営面で快く協力をして頂いた事務担当の佐藤さん、大池さんに心より感謝申し上げます。お陰様で研究費やり繰りの悩みが半減し心穏やかに研究に専念することができました。
上記の准教授達や竹岡講師始め全てのスタッフの皆さん、総勢で70名弱の大学院生や共同研究者の皆さんには、愉快な時を過ごせたのであれば嬉しく思いますが、辛い思いや不快な思いをさせたかもしれません。私自身顧みて、至らぬこと、恥ずかしきことの数々で心が痛む時が少なからずありましたが、気付かずにいたことも多々あったかと思います。この書面を借りてお詫び申し上げたく思います。
研究活動のための組織構築面の仕事として、赴任した加齢適応研究センターが時限付き組織であったため、大学院独立専攻へと改組することが大きな挑戦でした。その際は,同期着任の能勢、鈴木教授,そして樋口教授らと議論しつつ理念作りをさせて頂き充実した作業を共有しました。また組織作りとして創薬の開発研究を進める為に大学発ベンチャー企業の創立という仕事がありました。その何れの場合も、小宮山淳先生には医学部長、学長として温かいご指導とご支援を賜りました。厚く御礼申し上げます。
また、催しのお世話を苦手としつつも,松本市で日本がん転移学会を開催するお役目が廻ってきた時、頼りの綱だった板野准教授が教授として異動して不安感がありましたが、後任の肥田准教授,藤井助教と事務の大池さんのお陰で学会屋さんにお願いもせず,手作りながらも無事に終了できたことを感謝をもって思い出します。その会では杉村隆先生(学士院院長、元国立がんセンタ-総長)のご臨席を賜り、山際勝三郎博士生誕150周年記念シンポジウムで「本当に良い仕事はノーベル賞受賞云々に関係無く残るものです。」というコメントを頂いたこと,学会友人達の温かいご協力とご支援が印象深く残っています。
赴任後1、2年間は、担当教室名が環境適応分野であったにも拘らず,環境に適応できずアレルギー体質が酷くなり、入退院を繰り返し皆さんに迷惑をかけ給料泥棒そのものと内心悩みました。しかし、内科の久保恵嗣先生や池田修一先生、耳鼻科の宇佐美真一先生始め諸先生達のお陰で,比較的短期間で研究生活を楽しめるまでに回復できました。有り難うございました。一方、当時自分の体で生じている炎症の分子機序を想像しつつ床に伏すのは結構楽しくもあり、教室で見出された自然免疫や炎症の要の一つであるASC分子には不思議な繋がりと愛着を感じました。
着任当時薬理学教授だった千葉先生には学生のスキー合宿に参加すべきと半強制で八方峰のゲレンデにゴンドラで登らされ「ここから滑り降りてみ」と言われ、恐怖を味わったことを覚えています。九州育ちでスキー場を見たことも無い40歳半ばの中年男には無理難題の地獄でした。しかし、同日初心者である2人の女子医学生と一緒にスキー学校で学ぶ機会を与えて頂き、インストラクターに家族連れと間違われ,私は少なからずいい気分で(奥さんと間違われた女学生には気の毒でしたが・・)スキーを楽しく感じる好機となりました。また、当時整形外科教授でちょっとおっかない感じの高岡邦夫先生には「スキーをその年齢でやるもんやない,怪我しても面倒みらへん。それよりもゴルフをやりなはれ」とのお勧めがありました。このお二人の先生には40半ばの手習いを施して頂き感謝しております。お陰で、今も色々技術改善を自分で試すことが面白く、それぞれ年に数回ながらも楽しみの一つとなっています。
科学活動は、当然ながら厳しい競争に曝され、眼に見える成果が評価されます。それはプロ研究者には当然のことであり必要なことと思います。その点での評価は兎も角、一方で、科学活動には眼に見えない大切な成果があると思います。研究生活のお陰で、自分自身の宇宙観、死生観等に大きなそして豊かなインパクトを受けましたし、素晴らしい方々との出会いを与えられ、それらは何にも代え難い成果と思えます。
大学院及び学部の講義では、コアとなる知識は当然ながら、むしろ考えるプロセスや、学びに伴う嬉しさや感動のようなものを伝えたい気持ちで臨みました。学生さんがどのように受け取ったかは分かりませんが、時に受ける質問やコメントを嬉しく感じました。特に、共通教育で科学論を哲学者篠原成彦教授達と目に見え難い価値を主張すべく開講し、授業での教員同士あるいは学生との議論は学生時代も含め大学生活で最も楽しく充実したひとときの一つとなりました。
大学は、人間社会のための利便性、有用性という見え易い価値を追求するHow to liveのため、そして人間が本来何であるか,その存在意義を問う見え難い価値を追求するWhy to liveのための学問・研究の場であると思います。時代の状況に依存せず,これらの価値追求を両輪として進む姿勢あるいは意識が健全で豊かな人間社会を築く上で必須と思います。信州大学がそんな研究教育の場として発展して欲しいと願っています。
20年間有り難うございました。
最終講義抄録
がん研究の個人史
—学びと克服の試み—
谷口 俊一郎
はじめに
大学紛争で混乱する中、取りあえず大学進学した。物理学を志していたが「原爆を生んだ悪の研究をやるのか?」と活動家に難詰され落ち込んだ。荒んだ雰囲気の中、虚無感が漂い、心を満たす何かを求めた。今思うと、短絡した非難に翻弄された自分が恥ずかしい。それは兎も角、図書室で分子生物学の本を見つけ、中高時代退屈に感じた生物学と異なり分子論的視点に胸が躍った。そして、不治の病とされるがんに興味を覚え、その基礎研究をすれば誰にも責められず、前向きに生きていける気がした。
大学院で生物物理系に進学し,課程半ばで医学部癌研に出向した。癌研で師匠となった馬場恒男教授には議論の度に叱られた。私ががんを単純に捉え過ぎるとのことだった。遂には、がんの病理解剖見学を命じられた。がんの複雑さを学ばせる教育だった。凄まじい転移や腹膜播種を眼の当たりにし剖検3例目位に激しい胃潰瘍発作が生じた。それ程にショックだったが、がんは多様かつ複雑で、更に転移が難治性の本質と感じた。そして、お叱りの意味を納得し従順な学生になった。しかし、複雑だからこそ分子レベルで単純に理解したい天邪鬼的気持ちはむしろ強くなった。
米国癌研究所(NCI)留学
NCIで故角永武夫博士の下がん研究に携わる機会を得、遺伝子工学的内容を希望したが、細胞骨格の生化学実験系立ち上げを依頼された。同僚が短期間で遺伝子解析結果を一流誌に発表する中、辛い思いをしたが、後に自分の研究を立ち上げる修練になった。当時のNCIではがん遺伝子研究が花盛りだったが、がん転移への関心は低調だった。帰国後、馬場研でがん化学療法研究に従事する傍ら、がん転移の分子生物学的研究を立ち上げた。それが重要と思う一方,誰もやってないので魅力を感じた。
がん細胞の遺伝子操作による転移研究
細胞骨格や転写因子に着目し遺伝子操作でがん細胞の転移形質を制御出来ること、そして機序を示す事が出来た。それらの成果で、癌学会奨励賞を受賞しがん特定領域研究費も頂ける様になった。
そして、臨床材料を用いた共同研究が始まり、がん細胞のみならず血管等宿主側要因も転移理解に重要と認識した。がん細胞の遺伝子操作が流行し始め、賑々しさを避けたくもあり、がん細胞からがん微小環境に視点を移した。そして、馬場教授後任として勝木教授が赴任され、研究室は発生工学一色となった。
宿主に着目した転移研究
—Calponin h1(CN)欠損マウス作製—
ヒト悪性腫瘍の血管でCN(アクチン線維の安定化機能あり)の鋭敏な減弱を見出し,それは血管脆弱化を招き転移が亢進する要因と捉えた。又、CN減弱はがん細胞が分泌するPDGF-B等に因る事が分かった。宿主細胞のCN減弱ががんの浸潤・転移亢進の一因になる事を示す目的でCN欠損マウス作製を試みた。
CN欠損マウスができた頃、信大医に異動が決まった。着任後、そのマウス形質を調べ、血管に加え腹膜も脆弱であり、がんの血行性転移及び腹膜播種が生じ易いことを確認した。解析は配属された竹岡みち子博士が協力してくれた。
宿主を守り同時にがんを攻撃する
可能性の提示
—CNによるがん性腹膜炎の予防的治療—
CN欠損とは逆にCN強制発現をマウス腹腔内中皮細胞に施しても無害で、がん細胞存在による中皮細胞間の開裂を防御できた。一方、CNをがん細胞に強制発現させるとその増殖や浸潤能は抑制された。そして、がんの腹腔内移植系でCN発現ベクターip投与によるがんの腹膜播種抑制と延命効果を確認した。以上の効果を示すCNの責任領域のオリゴペプチド(同定済み)によるがん腹膜播種抑制が今後期待される。
がんの不安定性理解への挑戦
がん細胞/宿主の遺伝子操作で転移制御できることを自験で学んだので、がん細胞不安定性の解析に挑戦し始めた。不安定性が難治性の原因である転移能や薬剤耐性をもたらす本質だからである。
不安定性のマーカを核異型性とし、そのトリガー探索を目指した。初代助教授相良淳二博士がこの挑戦に賛同し協力してくれた。まず、核と細胞質の骨格に対する抗体ライブラリーを構築した。そして、核形態変化を誘導できるHL60細胞を用い、誘導前後で質的/量的変化をする分子を抗体で探索した。核形態制御の直接的責任分子は未発見であるが、ASCやScapinin等の新規分子を見つけた。
—ASC発見とその機能解析—
ASCは細胞核近辺に凝集するアポトーシス促進分子として見出された。初代院生の増本純也君(現愛媛大学医教授)が構造と機能解析で奮闘した。その後、ASCがカスペース1の活性化因子として欧米で示唆され、細胞質での自然免疫反応体(inflammasome)形成のadapter的役割が判明した。 ASC欠損マウスを院生山本雅達君(現鹿大医助教)が作製し、ASCのカスペース1活性化能を個体レベルで証明した。ASC欠損マウスは感染、発がん、免疫・炎症が関わる種々の病態解析で広く用いられている。
ASC機能を更に解析すると、核移行、細胞骨格との相互作用、また非増殖期にあるがんの細胞死誘導等、多様で興味深い事実が判明しつつある(論文準備中)。また、ASCと結合する蛋白質、Fascin、ががんの運動亢進と免疫回避の双方に働くという注目すべき現象を3代目准教授肥田重明博士と院生松村富穂君が見出し分子機序も解明した(論文準備中)。
また、ASC遺伝子にはCpG-islandsがあり、メチル化でその発現は変動し易い。その機能が多様である事も考え合わせると、ASCはがん形質不安定性に関与すると示唆される。
—Scapininとその機能解析—
ASCの他,興味深い新規分子Scapininは脱リン酸化酵素PP1阻害能、アクチン結合能、細胞膜から核内と多様な分布を示す。相良博士が機能解析を継続しているが、がん形質の不安定性,核形態制御への関与解明が期待される。
—細胞外骨格分子ヒアルロン酸の研究—
相良博士の後任助教授板野博士は乳癌を発生し易いマウスの乳腺にヒアルロン酸合成酵素を特異的発現させる系を構築しがんの微小環境の研究を見事に展開した。がん幹細胞のニッチとしてヒアルロン酸の役割解明が注目されている。
スポーツ医科学との共同研究
—運動処方のエピジェティックスー
能勢博教授が開発したインターバル速歩の効果評価に、被験者血液DNAのメチル化を調べ興味ある結果を得た。院生だった中島弘毅氏(現松本大教授)の解析によると熟年者への運動処方でASCメチル化が若者レベルに近づいたのである。更に、ゲノムワイドでメチル化を調べた所、本運動処方は抗炎症的と示唆される結果を得た。血液DNAのメチル化測定は諸臨床検査にも有用と思われる。
癌の不安定性を考慮したがん克服の試み
—固形がんの低酸素環境を利用する治療—
以下に述べる治療研究は,癌細胞での発現が不安定な分子(モノ)を標的とせず,その不均一集団の低酸素状態(コト)を安定な標的として腫瘍局所で大量かつ持続的に抗がん分子を産生し不均一集団丸ごと攻撃する試みである。
私が院生時代に始めた嫌気性ビフィズス(B)菌による固形がん標的の研究を信大就任講演で余談的に紹介した。藤森実先生(当時2外講師,後に東医大教授)が興味を示され、研究を再開することになった。追試の為、B菌を担がん動物に静注すると,がん選択的に生着・増殖し正常組織からは速やかに消失することが確認できた。そして制がん剤5FUの前駆体5FCを5FUに変換できる酵素を発現するB菌を樹立した。その菌を静注し、低毒性の5FCを経口投与すると固形がんのみで5FUが産生され,副作用無く抗腫瘍効果が得られた。B菌の安全性を認め、生物製剤開発を目的とするベンチャー企業が設立された。開発研究が進み、米国FDAとの交渉を経て臨床試験に至った。現在の所、深刻な有害事象は無く、5FUががん組織のみで検出された。
今日がん治療は分子標的薬やimmune check-point(ICP)阻害剤が注目されている。ICP阻害剤の抗腫瘍効果が画期的だが、自己免疫疾患様の強い副作用、又その超高価格が深刻な問題である。これらを改善すべくICP阻害単鎖抗体を腫瘍でのみ持続的に産生分泌できるB菌を樹立し,第2弾の製剤化を目指している。
おわりに
がん研究に携わって約40年,信大で約20年が過ぎた。がん基礎研究とがん治療研究に携わったが、前者ではミクロに、しかし後者はマクロに拘った。がんという不均一集団の攻撃には、細胞(モノ)よりも集団の状態(コト)特徴を標的に丸ごと狙う方が合理的と思うのである。
研究概要を述べさせて頂いたが、実験場所もない立ち上げから苦楽を共にしてくれた同僚や大学院生,そして出会えた共同研究者の皆さんに感謝である。
この間3名の准教授、2人の院生、そしてベンチャー活動を共にした藤森先生、ASC欠損マウスをフル活用し循環病態でのinflammasomeの重要性を指摘された高橋将文先生らが教授に昇進した。彼らと共有したコンセプトや夢の一部が継承され、発展すれば幸いである。
見える形での成果は兎も角、見え難い成果としてがん研究での学びは多い。例えば,計画死遺伝子の存在に驚いたが、それは多細胞系の形態形成や生存の為に必要なのだ。がんは計画死から逸脱し個の生存力は獲得するが,自分の居場所、宿主,を障害し結局破滅の道を辿る病気だ。このことは、私達は死につつ生きていること、個人の死が人間社会の存続に必要と気付かせてくれる。この学びは忌み嫌われる死の捉え方に少なからず良き意味で影響した。
さて定年退職は功績の多寡に拘らず職場の存続に大いに寄与できることになる。自他ともに喜ぶべきことと思うのはがん研究成果のひとつと思う次第である。
自著とその周辺
10代からの「いのち学」―あるがん研究者のつぶやきー 谷口俊一郎

(オフィスエム 2012年9月刊行)
【信州医誌2013年 Vol.61 No.6より(信州医学会許諾)】
「第22回日本がん転移学会学術集会・総会を振り返って」 谷口俊一郎 2013.8.29
第22回日本がん転移学会学術集会・総会が、松本市ホテルブエナビスタにおいて平成25年7月11日・12日の2日間にわたり開催されました。本学術集会は、「がんの不均一性-理解と対応-」をテーマとして掲げ、信州大学大学院医学系研究科の分子腫瘍学講座が事務局としてお世話致しました。
分子生物学的研究法の導入によりがんの研究は著しく進展し、特に、今日がんの分子標的治療薬の開発は目ざましい進歩を示しています。しかしながら、耐性細胞出現による再発や遠隔転移が生じるために充分な延命効果をもたらすという意味では依然困難があり、 がん治療法の課題・問題は依然として残されています。この薬剤耐性および転移形質はがん細胞が不安定で形質が変化し、薬剤耐性形質の獲得、浸潤能や転移能を獲得することから生じてきます。つまり、治療の困難さはがん細胞集団の不均一性に起因すると考えられるのです。従って、これらの根本的原因となっているがんの不均一性という古くて新しい問題を検証し今日的理解をすること、 さらにその問題解決のための糸口について討論することが必要と考え、上記のテーマを設定しました。
総参加者数は294名、総登録演題数は141題に達し、松本の地が地方都市であるにも拘らず、多くの研究者が集い、学術集会を一応盛会裡に遂行できた、と考えています。これもひとえに皆様方の温かいご支援とご協力のお蔭と、まずは深く感謝申しあげます。
本学術集会は、1つの教育講演を設定し、数理生物学者である阪大の鈴木 貴先生に「がん研究の新しい数学ツール~ホモロジー検査と数理細胞生物学」というタイトルでがんという複雑系を数学的視点から情報を解析するお話しを伺いました。 がん研究に新視点の導入が必要と考え、このような講演を設定しました。演者の先生には数式をなるべく使わず、考え方、利点、今後の期待できる点など新規コンセプトを懇切丁寧にご説明頂くようにお願いしました。できるだけ聴衆の皆さんが敬遠しないようにと気を揉みましたが、皆さん興味もってお聴き頂いたようです。恐らく日本のがん関連学会では初めての試みで、どうなるか多少不安でしたが、非常に新鮮で興味深い内容でした。
3つのシンポジウムでは、それぞれ①がんの不均一性の基礎的側面、②不均一ながん集団を攻撃する手段としてがん微小環境に焦点を合わせたセッション、そして③最新のがん治療・診断の情報交換を意識した内容のものを設定しました。さらにそれぞれのシンポジウム内容に対応する8つのワークショップを設けました。いずれのセッションも、がん幹細胞、ジェネティックス、エピジェネティクス、炎症、血管、間葉系細胞、細胞間相互作用やイメージングなど先端的あるいは重要な視点を提供するトピックスに満ち、討論も熱が入り時間オーバーすることしばしばでした。タイムキーパーとしての主催者側は冷や汗ものでしたが、ある意味うれしい悩みでした。
English sessionは権威あるBig Shotsよりも次世代を担う研究者を意識して外国から若くて秀でた仕事を展開している研究者を招待し座長も演者も本学会奨励賞受賞者の若手で構成しました。ポスターセッッションは多くの参加者の白熱する議論の故か、文字通り部屋が暑くなり空調を急冷に設定し直す一幕もありました。
特別企画として山極勝三郎生誕150周年記念シンポジウム(市民公開講座形式)を本学会と信州大学と山極勝三郎博士顕彰会との共催で2日目の午後のセッションで行いました。市民の方々はもちろん、多くの学会員が最後まで熱心に参加して頂きました。 この特別企画は先端研究成果を重視しつつも先人の業績に敬意を払い顕彰する精神を大切にしようという訴えのつもりで設定しましたし、また、信州の誇るべき山極博士を松本の地でアピールし地元の学生さんを鼓舞したいという気持ちもありました。このシンポジウムでは第一演者として本学の中山淳教授が糖質に焦点を合わせたピロリ菌と胃がんの発生の話題を分かり易く紹介して頂きました。続いて、山極勝三郎博士が主催した東大病理学教室の現教授でありTGF-β研究の世界的リーダである宮園浩平先生に発がんと進展に関するご講演をして頂きました。またがん哲学外来で著名な順天堂大学教授であり本学の客員教授でもある樋野興夫先生には「山極勝三郎&吉田富三の温故創新」というタイトルで一般の方々も興味を引く内容で講演をして頂きました。主催者側の挨拶としては、栄光ある研究成果の陰には、必ずその支えをした働き手がいる、そのことを忘れぬようにしたいということを申し上げ、山極博士のお仕事を実際に担当した市川厚一博士の功績にも触れました。
企業のご協力による3つのランチョンセミナーは、いずれもがん転移研究のトピックスが先端研究者によって紹介され大変好評でした。
この他、今回は当初冗談半分本気半分でネガティブデータのコーナーを設けましたが、幸か不幸か投稿はありませんでした。患者さんに焦点を合わせる本学会の理念から、国際的に注目される先端的データも必要ですが、治療進展のためにはネガティブデータも大切であると主張したかったのであります。また、製薬企業関連の研究者と話す機会があり、その雑談の中で大学の先生方の再現性に乏しいチャンピョンデータは役にたちませんという辛辣な言葉が脳裏に焼き付いていたためでもありました。また、名誉欲、研究費獲得あるいは昇進のための激しい競争故に、データのねつ造、盗作など忌まわしい出来事が散見されることを鑑み、見栄えに囚われず地道に着実に研究を進捗させる姿勢を大切にしたいという訴えの気持ちもありました。
今回の学会を通して特筆すべき事の一つとして、国立がんセンター名誉総長である杉村隆先生が開会の辞から閉会の辞まで休むことなく参加され、常に熱心にメモをお取りになり、そして質問コメントをなさる姿があったことです。このようなお姿は、私達後進研究者に無言で研究者としての真摯な姿勢を大いに教えて頂いたと思いました。また、杉村先生には特別企画の山極勝三郎生誕記念150周年記念シンポジウムで特別発言を賜り、「幻のノーベル賞受賞者としての山極博士ということをよく聞くが、真実を示した方の功績は周知され顕彰されるものであり、何賞を取ったなどにあんまり拘る必要はないのではないか。彼の功績は受賞の有無に関係なく称えられるべきものである。評価や名誉を求めるのみではなく、真実を真摯に求める姿勢を大切にすべきである」という内容のことを仰いました。この言葉は、私どもの、少なくとも私においては研究史観や姿勢において大切な視点を再確認する機会となりました。
会員の皆様には、今後の課題と新たな挑戦すべき点をお持ち帰り頂ける機会になったのではないかと思っております。有意義な情報交換の場となる各セッションをご担当頂きました座長およびスピーカーの先生方に感謝と御礼を心より申し上げたく思います。がんの不均一性はがん細胞の生存・進展に本質的であり、その理解と対応に一歩でも近づけるよう、さらに精進したいと主催者側も思いを新たに致しました。多様で不均一なことはがん治療において困るものの、多様で不均一な研究者の研究背景・視点・取組は、本学会の進展に重要な力であるとの思いも新たにさせられました。
本学会のようながん関連で全国レベルの学会開催は松本市では初めてのことと思います。ポスターや抄録の表紙では3がく都としての松本市の魅力をアピールすることに拘りました。そのことを通して多少なりとも地元に貢献できたのであればうれしく思います。
本学術集会・総会の開催に際しましては、予算節約のために学会事務を外部に委託せず、教室関係の少数スタッフを中心に準備・運営を行いました。教室のスタッフの協力と献身的頑張りには感謝してもしきれません。また、本会の開催・運営にご協力・協賛頂きました企業・団体各位に心より厚く御礼を申し上げたいと思います。以上感謝をこめてご報告とさせて頂きます。大変有難うございました。
「転移研究雑感」 谷口俊一郎 (日本がん転移学会ニューズレター(Vol.39)より)
今年2012年は9月にMRSの国際がん転移学会がオーストラリアのブレスベンにてErik W. Thompson博士を会長として開催されます。これに際し、日本がん転移学会は若い研究者主体のセッションの設定を提案し、それが実現することとなりました。日本がん転移学会の奨励賞を受賞なさった方々は、そのセッションでの発表をすることになっています。本年7月には安井会長による広島での日本がん転移学会が開催されます。両学会に皆様奮ってご参加下さい。特に、若い方々がご自己研鑽の場として頂きたいと思います。
今日、がん転移研究に限らず、ライフサイエンスの先端的研究が大変な勢いで進展するのは歓迎すべきかつ喜ばしいことで、自分達もその中で多少なりとも貢献したい、と願っています。一方、ビッグサイエンス化が著しく、激しい競争と評価の中で、研究費助成策が資本主義化し大きな大学・研究所と地方大学の格差が年を経るごとに加速されている現状があります。このような状況下、地方大学は、中央の動向と情報を注視し時代の流れに乗り遅れまいと心を砕くのではなく、地方大学が持つべき独自のミッション、そして研究や学問の楽しさと喜びを次世代に継承するという内面的豊かさを見失わず、また状況に一喜一憂せずにいたいものです。
生産性の高い所に研究費を重点配分する方法は、日本全体の平均値を上げる施策として妥当と思いますが、地方大学は予算と教員の削減にあえぎ、そしてポスドク、大学院生の獲得に苦労が増しています。ただ、こんな状況下であっても、あるいはこのような状況であるからこそ、地方大学で働く研究者として、何ができるか、地方大学の役割は何であるのか、と考えたいと思います。比較的ゆったりした時間の流れと豊かな自然は次世代への大切なシーズを育むのに良き環境です。大きな大学・研究所が先端的国際競争に多忙な大手デパート的役割があるとすれば、地方では良き意味での田舎の新鮮な香りがする品をじっくり育てる特産品販売の役割を担いたい、担うべきと思います。江戸時代にお百姓さんが、幕府政策「生かさぬよう殺さぬよう」によって、貧困で苦しい生活を強いられておりました。ただ、「殺さぬよう」というのは、やはり食料を生産してくれるお百姓さんの大切さを認識していたからでしょう。それと類似性を論じるのは、不謹慎かもしれませんが、今日地方大学の研究を大切にする施策、研究を維持継続する最小限の手当て、の必要性を感じます。行き過ぎの合理化は平均値アップには効果的であっても、地方の大切なシーズを失い易く、大きな損失になるからです。地方大学には数が多くはないかもしれませんが、地味ながら大切なシーズがありかつ生まれ育つ土壌がありますので、日本の活性化と将来のために大切にしなければならないと確信します。地方の中小企業が宇宙開発の要となる部品を提供しているように、私の同僚もその数は少ないかもしれませんが、インパクトと質が高い成果を挙げています。私達のチームも、地方のゆったりした環境だからこそじっくり系を立ち上げ細胞死・炎症制御に重要な分子ASCを見出し、自然免疫とがんとの関わりを勉強する機会が与えられましたし、非常識な発想と非難を受けながらも大学発ベンチャーの立ち上げと臨床研究に至る開発研究ができたと思います。
がん転移と対峙する医者や研究者は、がん細胞の不安定性による不均一集団であることが治療を困難にしていることを理解すると思いますが、このことは逆に不均一とマイナーなポピュレーションの存在がその集団全体の逞しさをもたらすことを知っていると言えます。日本各地の多様で目立たぬポピュレーションとして存在するシーズそしてそれを育む土壌を大切にする姿勢の重要さを、転移を学びその研究に携わる者として主張したいのです。
松本における2014年の本学会総会では地道にがん転移の本質であるがん細胞の不均一性の理解とその克服について、基礎的に、臨床的にそして歴史的に検証しつつ、道を模索したいと思います。ご理解とご協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
* ”ボケておりました、2014年は2013年の間違いです.申し訳ありません”
特集ヒト-細菌共生系の驚き
「嫌気性菌をがんへの “運び屋” にする」 谷口俊一郎
ヒト腸内細菌を固形がん治療 に臨床応用しようという研究が 進んでいる。その発想の源,科 学的根拠,将来性は,どのよう なものか。
今日最も確実ながん治療法は 早期発見と外科手術であるが, 転移がある場合,化学療法が一 般に適用される。最近のがんの 分子生物学的研究によって分子 標的薬が登場した。しかし,固 形がんの化学療法には,副作用, 薬剤到達性の不充分さ,そして 特にがん細胞の多様性に起因す る薬剤耐性などが,依然課題と して残されている。そこで,が ん細胞の微視的特異性もさるこ とながら,むしろその集団の巨 視的特異性を利用し,耐性を克 服すべく大量の薬剤をがん組織 に選択的に運び込むという発想 が生じた。
固形がんの低酸素状態は放射 線や化学療法に抵抗性である理 由として知られ,最近では腫瘍 の悪性化条件としても注目され ている。厄介視されてきた低酸 素状態を特異性として逆用し, 固形がん治療に非病原性嫌気性 菌を薬の運び屋とすることを考 え,研究と開発が進められた1。
がん治療のためとはいえ,菌 の血中投与は,非病原性であっ ても敗血症をもたらす非常識な発想とみなされてきたが,最近 『Nature』誌の総説に菌による がん治療が登場した2。遺伝子 工学は菌による医薬品産生を可 能にし,近年は菌の利用も腸内 から,口腔内,皮膚にも広がっ ている。がん治療への応用が常識となる日は近いかもしれない。 「嫌気性破傷風菌の芽胞を静 注すると,がんをもたせた動物 は死亡し,がんのない動物は無 症状である」という報告3は, 固形がんが低酸素状態であるこ とを生物学的に示唆しており, この学びをもとに非病原性ビフ ィズス菌を用いた固形がん標的 の研究が始められた。菌は静注 後,正常組織から数日間で消失し,悪性腫瘍部位のみで増殖し, 全身毒性は認められなかった4。
この発見から約 20 年が経過 し,cytosine deaminase(CD)遺伝 子の発現ベクターが導入された ビフィズス菌が作製された1。 この菌は静注後,固形がんで選 択的に増殖し,CD の働きによ って制がん剤 5FU(毒性は低く CD によって 5FU になる 5FC を経口投与す る)をがん局所で特異的に産生 し,抗腫瘍効果をもたらした。 この菌による著明な毒性所見や アナフィラキシー・ショックは 認められなかった1。これらの 成果をもとに大学発ベンチャー企業アネロファーマ サイエンス(株)が設立 され,がん治療のための 生物製剤開発が始まり現在 に至っている1。
米国では,NIH チームによ ってサルモネラ菌,ジョンス・ ホプキンス大学チームによって クロストリジウム菌を用いるが ん治療の臨床試験 Phase 1 が行 わ れ て い る(http://www.clinical trials.gov/ct/)。これらは弱毒化 したとはいえ病原菌であり,ビ フィズス菌は安全性で勝ると考 えられる。今後は種々の抗がん 性をもたらす産物としてサイト カイン,血管新生阻害蛋白質, プロドラッグ(代謝されて働く)の 活性化酵素や shRNA(特定の遺伝 子の発現を抑える)などを産生する 菌を開発し,それらによる併用 治療が期待される。ビフィズス 菌の安全性は好都合であるが, この菌の感染免疫面での詳細な 解析はきわめて重要であり新知 見が期待される。
文献
1―S. Taniguchi et al.: Cancer. Sci., 101 (9), 1925(2010)
2―N. S. Forbes: Nat. Rev. Cancer, 10 (11), 785(2010)
3―N. T. Kimura et al.: Cancer Res., 40 (6), 2061(1980)
4―R. A. Malmgren & C. C. Flanigan: Cancer Res., 15(7), 473(1955)
(訂正とお詫び:申し訳ありません。文献 3と4は逆です。)
【科学 0219 (岩波書店許諾)】
「WhyとHow」―医学研究での学び 谷口俊一郎 2009.01.30
大学紛争真っ盛りの大学に一応入学したものの、荒んだ雰囲気で失意と後悔の学生生活だった。そんな中、受験生活ではじっくり考えられなかった「数、言葉や物質の起源」について思いを馳せ、また考えること自体はどういうことかなどと、下手の考え休みに似たりの日々を過ごした。また、何の為の学問か、そして自分の存在の意義は何かと問いが広がると、答えの無い世界に迷い込んだ。政治活動家には「お前が専攻している物理学は原子爆弾を作った、けしからん」という非難を、今でこそ理不尽で短絡した非難と思うが、まともに受け入れ素朴な心を痛めた。まさに、「17,18,19と私の人生暗かった」という歌謡曲歌詞そのものだった。そのうちに、生きているという実感を与えてくれそうな生命科学、世の為になると言い訳できそうながんの研究に興味を持ち、大学院では生命科学系へと進んだ。物理の指導教官には留まるよう諭されたが、聞く耳は持てなかった。そして、その助言を無視したことに少なからず後悔の念を引きずりつつの根無し草的研究生活が始まり、今日に至っている。
そんな状況下、気分が充実している時は物理や数学の本を読んだが、憂鬱になると「生命科学」を勉強し、生きている実感を味わおうとした。ある時カルナップ著「物理学の哲学的基礎」をひもとき、「科学は事象の背後にある意義すなわち形而上的意義を求めて何故(Why)と問うべきではなく、ありのままを如何に(How)と問うて形而下的事象を記述すべきである」という一文を見出し、わが意を得たりと思うと同時にそれまで受けた科学教育の中で自分が何を悩んできたかを改めて確認し、歴史上の科学革命を自分の中で追体験できた。従来、何か分かった気がしないと悩んできた自分を振り返り、WhyとHowの問いの混同故と明確に認識したのである。しかし、同時に科学ではWhyに対する答えが得られない虚しさを改めて感じた。それから約35年過ぎた今、Whyという問いは重要であり、それが伴う動機がなければ自然科学は面白くないし、逆に自然科学がHowと問いかけ、自然のありのままを謙虚に記述した成果はWhyと問う自分に大きな影響を与え得ることを学んだ。
今日、科学は形而下の問題を扱うと常識化したためか、WhyとHowを意識的に区別する自然科学者は少ない。WhyとHowに私が拘る理由は、自然そして人間存在の目的や意義という形而上的問い(Why)、自然そして人間の仕組みや在り様に関する問いあるいは生きる術という形而下的問い(How)、それぞれを尊重しつつ互いに区別することが諸々を明確に理解するために必要と思うからである。目に見えない真理があるし、目に見える真理があり、それぞれ重要であり、いずれに偏っても健全ではない。
自然科学研究の中でも医学研究と取り組みWhyと問う自分が大きく影響を受けた学びの一例は「細胞計画死」である。これは今日のがん研究でも重要な領域を占め私自身も関わっている。「細胞には核があり、そこには宇宙の知恵」が詰まっていると宮沢賢治が言った。生きる為の情報がDNAの中に書かれ、そのことによって地球における生命の流れを維持してきたと思うと「宇宙の知恵」と言う表現に対し然りと頷ける。一方、「細胞計画死」の研究は、そのDNAの中に死ぬための情報も書かれていることを明らかにした。生と死の情報が共存しているという、この驚くべき事実は私達の生命が如何に制御されているかというHowという謙虚な形而下的問いの結果、見出された。しかし、この事実は何故生きるのか、何故死ぬのかというWhyという形而上的問いに対して、大きな影響を与えた、少なくとも私自身には、大変なインパクトがあった。「細胞計画死」は私達の個体が健全に生きるために必要なのである。「細胞計画死」が出来ないと自己免疫疾患やがんという病気になる。また、個体の死がなければ、地球上の生命の存続はできない。死によって個体がそして大きな生命の流れが存続しているという現実を再度学習した。何かしら、死に対する恐れや忌み嫌う先入観が薄れ開放感を伴う積極的意義を見出した喜びがあった。「細胞計画死」の学びは、一見冷たくあるいは無味乾燥にHowと問う科学が、Whyという答えの無い問にも拘る私に温かい何かを提供してくれたように思う。形而上的事柄と形而下的事柄のフィードバック的相互関係を体得した喜びがあった。医学研究に携わっていてよかったと思った一例である。
【信州医誌2008年6月号の巻頭言より改訂(信州医学会許諾)】
「私のがん転移研究-昨日、今日、明日」 谷口俊一郎 (日本がん転移学会 ニューズレターより)
私ががん転移研究に関心を持ったのは理学研究科・生物物理系の教室から九大医学部癌研に出向中、がん病理解剖の見学実習をさせられた時のことである。そんな経験をする羽目になったのは、その当時の癌研馬場恒男教授の命令であり、それは胃潰瘍を患うほど強烈だった。
癌研に出向したのは、大学紛争の影響もあって基礎研究の意義に悩み、より直接的に世に役立ちそうながん研究に従事したかったからである。癌研の先輩から「飛んで火に入る夏の虫」と言われたが、確かに、カルチャーショックは大きかった。安易に単純化と一般化を行おうとする私の習い性が教授の癇に触ったようで、議論の度にバカ者とよく怒鳴られた。「Over-simplificationをするな!同じ胃癌でも俺の胃癌とお前の胃癌は違うのだぞ。分かるか!」「先生と私の顔が違っても、目が二つ、口が一つと共通性の追求が科学でしょう」「分からん奴だ。亡くなったがん患者さんを自分の目で見てこい!」というやり取りを昨日の如く鮮明に思い出す。
がん性腹膜炎や肺転移のがん患者さん5,6例の病理解剖を目の当たりにし、がんは複雑系かつ各論的であると納得し、治療は転移との戦いと感じた。分子の学びからがん研究を目指し始めた者とがんを全身病として捉える病理学者の見識の差を痛感し、辛く貴重な体験となった。その後、議論は控え実験に専念したが、この複雑系を分子の言葉で単純化したいという内なる思いは逆に強まった。
その後、米国NCIの故角永武夫妍に留学し、がん遺伝子発見真っ最中の賑々しい雰囲気に触れた。しかし、当時話題にもならない転移性に関わる遺伝子研究が重要と感じて帰国し、馬場妍の主題である治療実験に再従事しつつ、転移関連遺伝子の探索を細々と開始した。そして、遺伝子操作でアクチン骨格系は細胞運動性を介して転移形質に直接関与すること、fos遺伝子は複数の遺伝子を介して転移形質に関わること、さらに、がん細胞作用による血管平滑筋や腹膜中皮細胞のアクチン骨格脆弱化が転移促進要因になり得ることを発生工学的研究で学んだ。
今日は遺伝子操作・遺伝子改変動物を用いた研究が日常化し、がんが遺伝子の病気であること、がんの発生と進展は遺伝子構造変化、あるいは発現変化の蓄積で生じることが常識になった。そして個々のがんの遺伝子変化が異なることから、がん個別療法の考えが生じた。「同種類の癌でも患者毎異なる」という恩師の主張は正しかったのである。しかし、それは単純化と一般化を目指す分子生物学的手法が解明した、と私の言い分にも一理あったと負け惜しみをしている。
がんの重要かつ根本問題は、J.Fidler博士が指摘された「がんのheterogeneity」と思う。がん細胞が不安定でヘテロ集団となり、より悪性のものが出現するということである。今日では、がん幹細胞の存在故にヘテロ集団が生じ大半は分化が進み自然消滅するという考えが台頭した。「がんのheterogeneity」という点で共通であるが、治療攻撃の標的として前者とは異なり後者はがん幹細胞のみとなる。がん幹細胞存在の普遍性、がん幹細胞以外は本当に自然消滅するのか、またがん細胞の幹細胞化への可逆性など興味と疑念は尽きない。また、幹細胞が一般にdormant stateであり薬剤耐性であること、がん幹細胞と正常組織幹細胞の選別などを考えると、新しい視点であるものの治療開発は従来同様容易ではないと感じている。「がんのheterogeneity」の実体がどうであれ、ヘテロ細胞集団の選択的壊滅に有効な方法の模索が大きな今後の課題と思う。
固形がん治療に必要な選択性を考える時、絵や写真作品を理解するに適切な距離のことを思う。離れすぎても作品が見えないが、近すぎると絵の具の塊や銀粒子のみが見えて作品そのものを理解できない。つまり、がん細胞の分子のみでなく、むしろもう少し離れてがん組織レベルを眺めることも重要と思うのである。固形がん組織の低酸素・低pH・炎症状態そしてそれ故に生じる血管構築・機能の異常に視点を移すと、特異的治療を困難にしている「がんのheterogeneity」やがん幹細胞の存在有無に依存せず、特異的攻撃を可能とする道があるのではないか。がん治療には「もの」と同時に「こと」の特異性に注目する必要を感じるのである。実際、私自身は固形がんにおける炎症状態、血管動態変化や低酸素状態に着目したがん治療研究を試みている。
がん転移学会は、がんの微小環境研究において研究者層が厚く、がん細胞の分子標的探索のみならず治療に有用な情報発信の潜在力があり、他関連学会と棲み分けられるようにも思う。当学会の設立に尽力なさった故明度先生など諸先達の夢、がん転移理解とがん克服、に向けてさらに進展する明日を期待したい。
 HOME
HOME