2025年 第2回「地域医療」(医学科4年生)
2025.7. 1更新
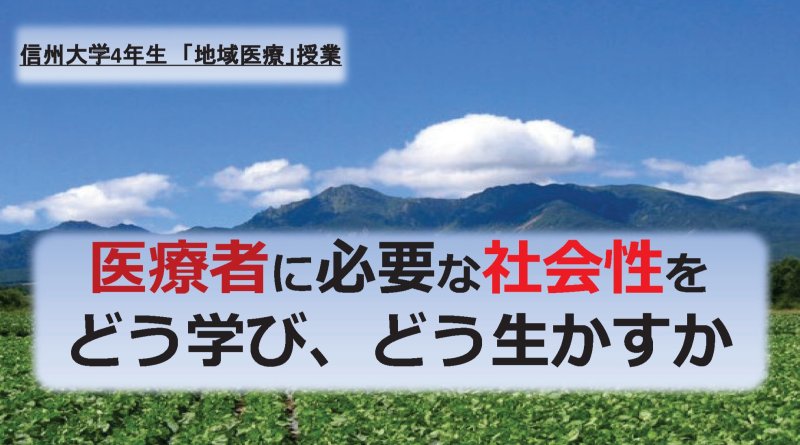
第2回目の信州大学医学部医学科4年生「地域医療」の授業では、佐久総合病院小海分院診療部長の小林和之先生にお話しいただきました。
以下が、学生の感想の抜粋です。
☆医師になるために医学を学ぶだけではなく、社会の中で活躍するために学ばなければならないことがたくさんあるんだと気づかされました。私も、必要であると感じたことはもちろん、自分の興味のある分野についても追求していきたいと思います。
☆言葉に深みがあって、教養と経験をつけると先生のようになれるのだろうかと憧れと不安を感じました。したいことに溢れていて前向きな姿勢で活動されている姿が印象的で、私も医師として働き始めた後も、向上心を忘れないよう努力しようと思いました。
☆総合診療科という名前に対する印象として、以前は「科横断的にみる」というような単なる医学的側面を指すものだと捉えていましたが、地域の交流や行政、サービスの構造といった市民の周りを取り巻く全てを評価し手を入れようとする視野が重要なのかなと感じました。
☆患者に寄り添うということの実例を知ることができた。しかし、想像以上に大変そうで、将来自分にできるのか不安になった。どこまでやるのかは医師それぞれの考えや目指すものによって変わるはずだから、自分が目指す医師像や考えをはっきりさせておく必要があると感じた。
☆今まで適当に使ってきた社会性という言葉を、深く考えるきっかけになった授業だった。社会性には、周囲の人との関わりが必要不可欠であり,それが一番具現化されたものが地域医療なのだと思う。また、授業中に触れていた、全体を知らないとわからない部分もわからなくなる、というのは今までもよく実感することが多かったように思う。
☆医療には想像力が必要なのだなとひしひしと感じました。私は想像力がある方ではないので、色々な人の経験、考え方、生き方を聞き、少しでも自分の世界を広げて生きたらよいなと思いました。
☆「地域医療とは田舎の方で医者をやること」程度の認識だった。けど実際の地域医療は全く違うことがわかった。医療を施すだけではなく一人一人の人と長期にわたって包括的に関わっていくことが地域医療であることを知り、それは大病院で最新の医学を学ぶことよりも難しいのではないかと感じた。患者ではなく一人の人として接し、その過程で経営を学んだり和歌を学んだりする姿に感銘を受けました。


