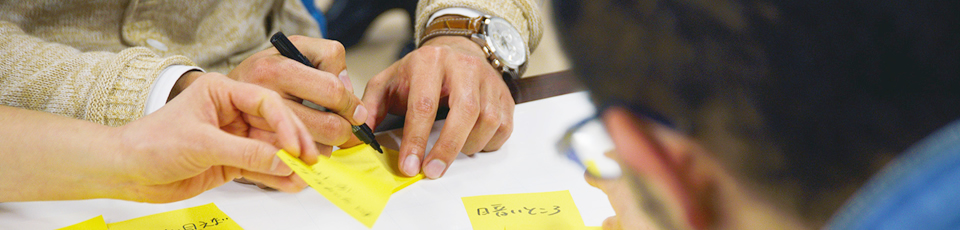
文部科学省「大学等シーズ・ニーズ創出強化支援(イノベ―ション対話促進プログラム)」事業は、2014年3月をもって終了いたしました。
ご支援、ご協力を賜りありがとうございました。
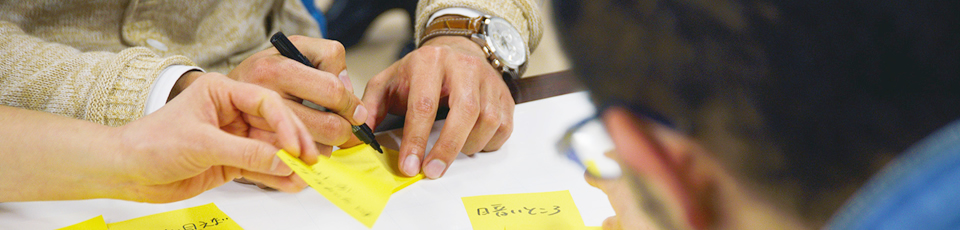


現在、社会が抱えている困難な課題を解決し、持続可能な豊かな社会を実現するために、イノベーションによる解決策の創出が必要とされています。大学の役割は、大学の資産である知識を、社会が本当に必要としている場所へ落とし込み、解決策を創出し、社会実装までを行うことにあります。
対話によって、多様な知的活動主体(大学、企業、市民、NPO、行政等)の潜在的ニーズを掘り起こし、あるべき将来像を引き出すことができます。さらに、多様な参加者の集合知を形成させ解決策に結び付けます。それにより、社会変革をおこしイノベーション創出につながる確率を高めます。


イノベーション創出には、対話を通じてそれぞれの参加者が有する知識や経験を掛け合わせて集合知を得ることで、潜在的ニーズの発見や革新的な解決策を創出することが有効と考えられます。集合知を得るために、参加者が意見を出しやすいプログラムや空間づくりの開発・試行を行っています。ワークショップの目的に応じて、ブレインストーミングで多くの意見を得たのち、様々な手法で意見を収束させることにより、参加者がこれまで気づいていなかった常識の外にあるアイデア(insight)を創出します。これにより新しい価値やこれまでの価値を変えるものを創造し、社会実装を目指します。
対話型ワークショップを4つのフェーズで実施します。第1フェーズ、第2フェーズでは、地域住民を始め、一般公募による参加者と信州大学の研究者、自治体職員、企業関係者を参加者として迎え、20-30年後の豊かな将来とは何か、豊かな将来にあったらいいモノ・コト(コンセプト)は何かについて対話を行います。
第3フェーズ、第4フェーズでは、前回のWSで導き出されたコンセプトについて、各分野の専門家を加えて実現要件(技術要件・制度要件)と普及要件(文化的・インフラなど)を明らかにし、解決策を対話により導き出します。20-30年後の豊かな将来を実現するための問題・解決策をまとめた「イノベーション・プロポーザル」を提案します。

ワークショップ実施を通じて、信州大学発のイノベーションを創出のための対話型ワークショップを補完する対話ツール開発を進めます。ワークショップのフェーズはそれぞれ異なる目的を有し、それらに対応した対話ツールを設計、テスト、改良し、よりよい対話ツールを目指しています。加えて、対話型ワークショップを先行して実施する国内外の機関・大学等への視察調査やヒアリングを通して我々の対話ツールのブラッシュアップに取り組んでいます。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント(SDM)による、文部科学省委託事業「イノベーション対話ツール」を活用し、対話型ワークショップに使用する発散・収束の手法や、ファシリテータを補完する道具、対話型ワークショップの成果物をプレスリリースやプロモーションビデオ、模型などによりまとめます。最終アウトプットとして『イノベーション・プロポーザル』を提案し、課題の明確化から、解決策の提案、アイデアの実装化までを一貫して促進するツール開発を試行します。

大学の産学連携活動強化によるイノベーション創出を促進するため、共同研究の推進や多様な知的活動主体をマネジメントする立場にある本学のリサーチ・アドミニストレーター(RA)に対して、ファシリテータ・スキルの向上を図っています。
長野県で自治体や地域住民を対象にフューチャーセッションを導入している特定非営利活動法人SCOPと協働し「実践型学習プログラム」を開発します。対話型ワークショップで多様な人材の対話をマネジメントする経験を通じて、対話型ワークショップに必要なチームデザイン、プログラムデザイン、およびファシリテーション能力の向上を図ります。
