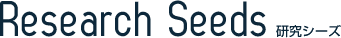スポーツによる血液性状変化とその機序に関する研究
スポーツによる血液性状変化とその機序に関する研究
【大分類:7. デサントスポーツ科学 小分類:7.9 Vol.9】
考案
運動選手に鉄欠乏性貧血が多いことはよく知られた事実であり,われわれもこれまで男子高校生運動部員について,運動が鉄欠乏状態を惹起することを報告した1).今回は,運動が実際に生体に対してどのような影響を与えているかということを知るために,運動前後における各種パラメータを測定し検討した.
さらに,運動強度の違いが生体に与える影響についても検討した,しかし,実際に運動強度の違いを数量的に表現することは困難であるために,どのようなレベルで運動を行なっているのか,つまり,どのような大会で勝敗を争っているのかということで運動強度の違いを推察するにとどまった.対照の男子高校生はほとんど運動をしない健常な生徒であり,K高群はいわゆる進学校に通学する男子生徒で,運動クラブに所属してはいるが運動強度は軽度で,地方大会の1〜2回戦レベルではある.それに対してT高群は,ほとんど毎日5〜6時間のかなりハードな練習を行ない,全国大会上位入賞あるいは優勝を争うというようなトップレベルの群であり,従ってかなり強度の運動を行なっていると考えられる.
末梢血液の成績では,赤血球,ヘモグロビン値,ヘマトクリット値はT高群で対照より有意に低下し,運動前後の検討では連動後で前値に比し有意に低下していた.これに対しK高群では,ヘモグロビン値のみが対照群に比し有意に低下していた.またT高群とK高群ではいずれもT高群が有意に低値を示していた(図1,2,3).
激しい運動をする人たちは貧血になりやすい傾向にあることは今までにも指摘されており2),K高群とT高群で有意に,また運動強度の強いほうでより強く貧血,傾向を認めた.これらの所見は,運動により赤血球が破壊され,その結果鉄分が経尿道的に,さらに発汗時の表皮細胞脱落とともに失われ3),それらが鉄喪失に関連し,さらに腸管からの鉄吸収が障害される等により生体内が鉄欠乏状態に陥り,従って運動強度の強いものが貧血傾向をより強く示すとする従来の報告4)と矛盾しないものと思われる.しかし,然血が赤血球およびヘマトクリット値低下の原因とするには,ヘモグロビン値も低下することの説明ができず,血液の希釈も一部関係5)していると推察される.
白血球については対照群とK高群は有意差なく,T高群でやや低い,傾向を示したが,運動前後の比較において運動後の値が有意に上昇していた(図4).白血球分画による検討により,リンパ球数は有意に低下したものの,正常築囲内であることから,白血球数の増加は好中球の増加によることが考えられ,これはmarginalpollからの動員によるもので生理的変動(運動による)の結果と考えられた(図5,6).
鉄代謝に関しては,運動前後で血清鉄の変化はみられなかったが,T高群は対照群,K高群に比して有意に血清鉄が低下しており,運動の軽度なK高群は対照群とは有意差を認められなかった(図7).また,TIBCは運動後に有意に増加し,従って飽和率は有意に低下した(図8).運動後にTIBCが上昇する理由はよく分かっていない.推察の域をでないが,TIBCプール(たとえば肝など)からの動員,ひいては鉄欠乏に有利に対応する生体の反応とも理解される.
それに関して,運動群でTIBCが正常域ではあるものの対照群より低値を示したことは,赤血球の低値を鉄欠乏のみで説明することは困難であることを示唆している.トランスフェリンは,鉄欠乏性貧血などの場合を除けばalbuminなどと相関して変動するといわれる.しかし,運動時は一時的に低タンパク血症になる6)ともいわれ,毎日激しい運動をするために血清鉄が低値を示すにもかかわらずTIBCが増加しないのは,トランフェリンの交替量の増加を示唆しているのかもしれない.
また,血清フェリチンは体内貯蔵量を反映し,その減少は初期の鉄欠乏状態(貧血のない)を知るうえに非常に有用な指標として現在広く使用されているが,対照群,運動前後ともに有意差は認められなかった.しかし,全群において正常値(135±58)を上回る者が多く,有意差は認めなかったものの,運動群は対照群よりさらに低値を示す傾向がみられた(図10).K高群において対照群より有意に低下したことについては,測定時期の違い(K高群は前回のデータを使用した)のほかに,食事による鉄補充の程度も関与しているものと推察される.つまり,いわゆるスポーツ貧血の発症予防には高蛋白食が必要との報告7)があるように,カロリーと蛋白質量の摂取が十分でないことが推察される.いずれにしても運動群では鉄欠乏状態にあると思われ,対照群でも血清フェリチンが正常値に比して低下傾向を示し,末梢血液データをも考えあわせると,運動群ではさらに強い鉄欠乏状態にあることが示唆された.
CPK,M-ALD,Mbは筋肉由来の酵素,蛋白であるが,運動前後の比較において,運動後に有意に高値を示した.CPK値はT高群が対照,K高群に比しいずれも有意に上昇(図13)していたが,K高群と対照群はK高群が高い傾向を示すが有意な差はなく,運動強度を反映していると考えた.これに対しMb値は,運動前後では運動後に高い値を示した(図14)が,CPKとは違って運動前,値は対照群と差がなく,K高群のみが対照群とT高群より有意に高い値を示した.これは,K高群の検体は運動後2〜3時間後のものであり,その影響によると考えられた.またK高群のCPK値がT高群運動前値より低値を示した点は,MbとCPKの血中半減期の違いによるものと推察された(半減期:CPK15h8),Mb5.5h9)).これらの所見はスポーツ筋症とも言い得る状態を反映するものと考えられる1).さらに,Mb中にも鉄が含有されていることから,スポーツ筋症に起因する鉄欠乏の存在することが示唆される.
ハプトグロビン(Hp)値とヘモペキシン(Hpx)値については,Hpが運動による溶血を示唆して低下(図11)しているものと考えられた.HpxはHpより溶血の影響を受けにくく,重症の溶血性貧血で低下する10)とされ,運動による溶血の程度では影響を受けにくい(図12)ものと考えられた.尿中ミオグロビン値は,今回の測定系の範囲内では運動前後ともほとんど認められなかった.ミオグンビン尿は筋細胞が大量にしかも急激に破壊される時に出現する11)とされ,今回尿中に出現しなかったことは,スポーツ筋症では筋肉障害の程度が軽いことを示唆するものとも考えられた.
「デサントスポーツ科学」第9巻/公益財団法人 石本記念 デサントスポーツ科学振興財団
運動選手に鉄欠乏性貧血が多いことはよく知られた事実であり,われわれもこれまで男子高校生運動部員について,運動が鉄欠乏状態を惹起することを報告した1).今回は,運動が実際に生体に対してどのような影響を与えているかということを知るために,運動前後における各種パラメータを測定し検討した.
さらに,運動強度の違いが生体に与える影響についても検討した,しかし,実際に運動強度の違いを数量的に表現することは困難であるために,どのようなレベルで運動を行なっているのか,つまり,どのような大会で勝敗を争っているのかということで運動強度の違いを推察するにとどまった.対照の男子高校生はほとんど運動をしない健常な生徒であり,K高群はいわゆる進学校に通学する男子生徒で,運動クラブに所属してはいるが運動強度は軽度で,地方大会の1〜2回戦レベルではある.それに対してT高群は,ほとんど毎日5〜6時間のかなりハードな練習を行ない,全国大会上位入賞あるいは優勝を争うというようなトップレベルの群であり,従ってかなり強度の運動を行なっていると考えられる.
末梢血液の成績では,赤血球,ヘモグロビン値,ヘマトクリット値はT高群で対照より有意に低下し,運動前後の検討では連動後で前値に比し有意に低下していた.これに対しK高群では,ヘモグロビン値のみが対照群に比し有意に低下していた.またT高群とK高群ではいずれもT高群が有意に低値を示していた(図1,2,3).
激しい運動をする人たちは貧血になりやすい傾向にあることは今までにも指摘されており2),K高群とT高群で有意に,また運動強度の強いほうでより強く貧血,傾向を認めた.これらの所見は,運動により赤血球が破壊され,その結果鉄分が経尿道的に,さらに発汗時の表皮細胞脱落とともに失われ3),それらが鉄喪失に関連し,さらに腸管からの鉄吸収が障害される等により生体内が鉄欠乏状態に陥り,従って運動強度の強いものが貧血傾向をより強く示すとする従来の報告4)と矛盾しないものと思われる.しかし,然血が赤血球およびヘマトクリット値低下の原因とするには,ヘモグロビン値も低下することの説明ができず,血液の希釈も一部関係5)していると推察される.
白血球については対照群とK高群は有意差なく,T高群でやや低い,傾向を示したが,運動前後の比較において運動後の値が有意に上昇していた(図4).白血球分画による検討により,リンパ球数は有意に低下したものの,正常築囲内であることから,白血球数の増加は好中球の増加によることが考えられ,これはmarginalpollからの動員によるもので生理的変動(運動による)の結果と考えられた(図5,6).
鉄代謝に関しては,運動前後で血清鉄の変化はみられなかったが,T高群は対照群,K高群に比して有意に血清鉄が低下しており,運動の軽度なK高群は対照群とは有意差を認められなかった(図7).また,TIBCは運動後に有意に増加し,従って飽和率は有意に低下した(図8).運動後にTIBCが上昇する理由はよく分かっていない.推察の域をでないが,TIBCプール(たとえば肝など)からの動員,ひいては鉄欠乏に有利に対応する生体の反応とも理解される.
それに関して,運動群でTIBCが正常域ではあるものの対照群より低値を示したことは,赤血球の低値を鉄欠乏のみで説明することは困難であることを示唆している.トランスフェリンは,鉄欠乏性貧血などの場合を除けばalbuminなどと相関して変動するといわれる.しかし,運動時は一時的に低タンパク血症になる6)ともいわれ,毎日激しい運動をするために血清鉄が低値を示すにもかかわらずTIBCが増加しないのは,トランフェリンの交替量の増加を示唆しているのかもしれない.
また,血清フェリチンは体内貯蔵量を反映し,その減少は初期の鉄欠乏状態(貧血のない)を知るうえに非常に有用な指標として現在広く使用されているが,対照群,運動前後ともに有意差は認められなかった.しかし,全群において正常値(135±58)を上回る者が多く,有意差は認めなかったものの,運動群は対照群よりさらに低値を示す傾向がみられた(図10).K高群において対照群より有意に低下したことについては,測定時期の違い(K高群は前回のデータを使用した)のほかに,食事による鉄補充の程度も関与しているものと推察される.つまり,いわゆるスポーツ貧血の発症予防には高蛋白食が必要との報告7)があるように,カロリーと蛋白質量の摂取が十分でないことが推察される.いずれにしても運動群では鉄欠乏状態にあると思われ,対照群でも血清フェリチンが正常値に比して低下傾向を示し,末梢血液データをも考えあわせると,運動群ではさらに強い鉄欠乏状態にあることが示唆された.
CPK,M-ALD,Mbは筋肉由来の酵素,蛋白であるが,運動前後の比較において,運動後に有意に高値を示した.CPK値はT高群が対照,K高群に比しいずれも有意に上昇(図13)していたが,K高群と対照群はK高群が高い傾向を示すが有意な差はなく,運動強度を反映していると考えた.これに対しMb値は,運動前後では運動後に高い値を示した(図14)が,CPKとは違って運動前,値は対照群と差がなく,K高群のみが対照群とT高群より有意に高い値を示した.これは,K高群の検体は運動後2〜3時間後のものであり,その影響によると考えられた.またK高群のCPK値がT高群運動前値より低値を示した点は,MbとCPKの血中半減期の違いによるものと推察された(半減期:CPK15h8),Mb5.5h9)).これらの所見はスポーツ筋症とも言い得る状態を反映するものと考えられる1).さらに,Mb中にも鉄が含有されていることから,スポーツ筋症に起因する鉄欠乏の存在することが示唆される.
ハプトグロビン(Hp)値とヘモペキシン(Hpx)値については,Hpが運動による溶血を示唆して低下(図11)しているものと考えられた.HpxはHpより溶血の影響を受けにくく,重症の溶血性貧血で低下する10)とされ,運動による溶血の程度では影響を受けにくい(図12)ものと考えられた.尿中ミオグロビン値は,今回の測定系の範囲内では運動前後ともほとんど認められなかった.ミオグンビン尿は筋細胞が大量にしかも急激に破壊される時に出現する11)とされ,今回尿中に出現しなかったことは,スポーツ筋症では筋肉障害の程度が軽いことを示唆するものとも考えられた.
「デサントスポーツ科学」第9巻/公益財団法人 石本記念 デサントスポーツ科学振興財団
| 研究者名 | 宮﨑保, 桜田恵右, 浜田結城, 大原行雄, 前吉俊, 上原好雄, 田中淳司 |
|---|---|
| 大学・機関名 | 北海道大学 |
キーワード