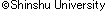7月22日、刑事訴訟法の授業で、模擬裁判を実施しました。

信州大学経済学部は、裁判員制度の理解を深めるべく、刑事訴訟法の講義において模擬裁判を実施しました。検察官は、現役の検察官である藤野晃俊検事(長野地検松本支部長兼諏訪支部長)に、弁護人は、本学の弁護士出身の池田秀敏教授に担当していただきました(裁判官は、担当教員の丸橋昌太郎専任講師が務めました)。そのため、本物の裁判を傍聴しているかのような迫真の模擬裁判となりました。 受講生は、各自が裁判員になったつもりで、殺意の有無や量刑を判断しました(評決の結果は下記参照)。受講生の感想は、「論告・弁論は理解しやすく、裁判員でも判断は可能だと思った」「法律に全く知識がない人であっても参加することは比較的容易であると感じ取れた。」という意見もある一方で、量刑についてはやはり判断が難しいという声も多数寄せられました。また、本模擬裁判を通じて、「裁判員の責任を痛感した。」、「実際に模擬裁判に参加することで裁判員制度の理解が高まったように感じる。」という感想も多く、受講生にとっては裁判員制度を考えるきっかけになったようです。
【その他の受講生の主な意見・感想】

●検察官も弁護人もわかりやすく説明する工夫をしていたと思う。難しい専門用語もあまりなくて理解しやすかったので今回のような工夫をしてくれたら裁判員になっても理解できるのではないかと思った。
●今まで裁判員制度にあまり期待をしていませんでしたが、意義のある制度であると思うことができました。
●裁判員制度は、国民が司法に参加でき、より関心を持つことができるという点では良い制度だと考える。しかし、人を裁くと言うことは難しいことだと感じた。
● このような模擬公判は初めて体験したが、素人にも理解しやすいように工夫されていると思う。ただ決して短時間とは言えないので、集中力が持続するかについては疑問が残る。集中力が切れて慎重性を欠く判断がなされるのであれば、裁判員制度を導入した意味も薄れてしまうのではないであろうか。
●実際に裁判員として裁判に参加すると、裁判のあと裁判官と議論することになるが、集中力がそこまで続くのか疑問に感じた。公判に対する予備知識や見るべきポイントなどをあらかじめ説明したり、裁判員についての知識をより深めるような政策が必要だと感じた。
●今回の模擬公判は争点が一つだけであったが、それだけでも様々な事情を踏まえて結論を出さねばならず、裁判員の負担は決して軽いものではないと思った。
●負担という意味では、裁判員だけではなく、検察官や弁護人の負担も大きいと思った。
殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(模擬)

信州大学地方裁判所平成20年(わ)第○○号
平成20年7月29日刑事第1部判決(模擬)
主 文
被告人を懲役12年に処する。
未決勾留日数中80日をその刑に算入する。
押収してあるペティーナイフ1本(平成○○年押第○号の○)を
没収する。
理 由
(犯行に至る経緯) 略
(罪となるべき事実) 略
(補足説明)
・裁判員数 120名
→過半数61名
・殺意の有無
有 107名
無 13名
→ 殺意有り
(法令の適用)
罰条
判示第1の行為 刑法203条,199条
判示第2の行為 銃砲刀剣類所持等取締法32条5号,22条
刑種の選択
判示第1の罪 有期懲役刑
判示第2の罪 懲役刑
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重)
未決勾留日数の算入 同法21条
没収 刑法19条1項2号,2項本文(押収してあるペティーナイフ1本(平成○○年押第○号の○)は,判示第1の殺人未遂の用に供した物で被告人以外の者に属しない。)
訴訟費用の処理 刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
(量刑の理由)
量刑に関する意見が3説以上に分かれた場合、過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による(法67条・)
| 量刑 | 評決数 | 累計 | 過半数 |
| 死刑 | 1 | 1 | |
| 無期 | 4 | 5 | |
| 15年 | 44 | 49 | |
| 14年 | 4 | 53 | |
| 13年 | 4 | 57 | |
| 12年 | 5 | 62 | ★ |
| 11年 | 1 | 63 | |
| 10年 | 27 | 90 | |
| 9年 | 1 | 91 | |
| 8年 | 6 | 97 | |
| 7年 | 7 | 104 | |
| 5年 | 7 | 111 | |
| 4年 | 1 | 112 | |
| 3年 | 2 | 114 | |
|
無回答 |
6 | 120 |
(求刑15年)
以上