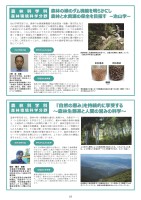農学部研究紹介2014|信州大学
19/47
治⼭学研究室研究から広がる未来卒業後の未来像治山学研究室では、森林の水源涵養機能や表面侵食・崩壊・落石防止などの山地災害防止機能、津波や高潮などの潮害防止機能、防風防霧防音などの多岐にわたる研究を展開しています。水源涵養機能については未解明な部分が多く、これらを明らかにするため大学演習林等に試験地を設け、気象・土壌水分・流量などの観測を行い、長期的なデータを取集しています。とくに、「森林の水源涵養機能の本質」とされている森林土壌の働きについて詳しく研究を行っており、土壌保全のための森林管理方法の開発を目指しています。水は私たち人間の生命維持に不可欠なものであり、毎日の生活にも欠かすことができない重要なものです。我が国の場合、水道の水のほとんどは、水源地帯である森林の土壌の中を一旦通過してきたものです。普段意識していないかもしれませんが、私たちの生活は森林と強く結びついているのです。水源涵養機能に大きく影響する森林土壌の働きを明らかにし、土壌保全につながる森林管理方法を開発することは、私たちの生命・生活を守ることを意味します。森林と人間が共生することは、私たちの生命・生活、そして森林を守ることにつながるのです。小野裕助教信州大学大学院、名古屋大学大学院を経て1990年より信州大学農学部。森林の水源涵養機能に大きく影響する森林土壌の働きに関心がある。現在、森林伐採に伴う土壌機能の変化について研究中。試験流域に流量観測施設を設けて、流量を長期的に観測している(信州大学手良沢山演習林)単粒構造の土壌に比べ団粒構造の森林土壌では孔隙(隙間)が多く水が浸み込みやすい森林の緑のダム機能を明らかにし森林と⽔資源の保全を⽬指すー治⼭学ー森林の持つ機能を、理論と体験の両面からとらえることによって、自然の重要性や、自然現象を貫く原理や法則を理解し、突発的に起こる事象への適応力が身につくでしょう。卒業後は国家や都道府県等の公務員、環境調査会社等で主体的に活躍できる人材となるでしょう。森林科学科森林環境科学分野造林学研究室研究から広がる未来卒業後の未来像造林学研究室では、森林の持つ諸機能を適切に発揮させ、生態系サービス(=自然の恵み)を享受することを目的に、樹木の挙動や森林の動態を、立地条件との関係から長期的に調べています。森林生態系は巨大なバイオマス、複雑な空間構造、多様な生物の相互作用によって特徴付けられる生態系です。その振る舞いを科学的な観点から観測し、地球温暖化の影響や、間伐等の施業の影響を抽出することで、森林生態系のグローバルな役割を長期にわたって維持させ、より良い人間社会の構築に寄与させることを、私たちは目指しています。私たちは森林生態学の立場から、変動する地球環境のなかで、森林と人間との関わり方を考えるための研究を行っています。森林生態系を理解する研究や、森林生態系を制御する技術開発を通じて、循環型社会の創出に寄与できます。私たちがターゲットとしている中山間地域は小さな自治体ですが、それは科学的な研究成果を政策に反映させ易いアクティビティの高いフィールドともなっています。森林生態系をモニタリングする能力、樹木の種を同定する能力、樹木の生き方を理解する能力が身に付きます。これらの科学的能力は、公務員や環境コンサルタントの分野において森林計画の策定と実行に活用されます。城田徹央助教北海道大学博物館産官学連携研究院等を経て2009年4月より信州大学農学部。人工林生態系の生物多様性創出、生態系サービスの制御、その地域活用を目的とした『人の関わる森林生態学』に関心がある。『⾃然の恵み』を持続的に享受する〜森林⽣態系と⼈間の営みの科学〜人工林でも間伐により生物多様性を高められる。このような人工林は、より充実した生態系サービスを発揮できるが、コストも高い。山地帯から樹木限界までの植物分布は、20年前よりも標高50m上方にシフトしていた。森林は地球温暖化のセンサーになっている。森林科学科森林環境科学分野1818
元のページ