研究内容
1.放線菌における染色体移行現象の利用
放線菌は抗生物質を生産する工業的に有用な微生物です。しかし物質生産に必要な遺伝子を外部から導入することが困難な種も存在しています。そこで遺伝子の導入に染色体移行現象を利用することを考えました。染色体移行現象は放線菌で確認されている染色体が細胞間で伝達される現象であり、これを利用すれば長大な遺伝子の導入、安定した遺伝子の保持が期待できます。この導入法を確立するため、研究を行っています。
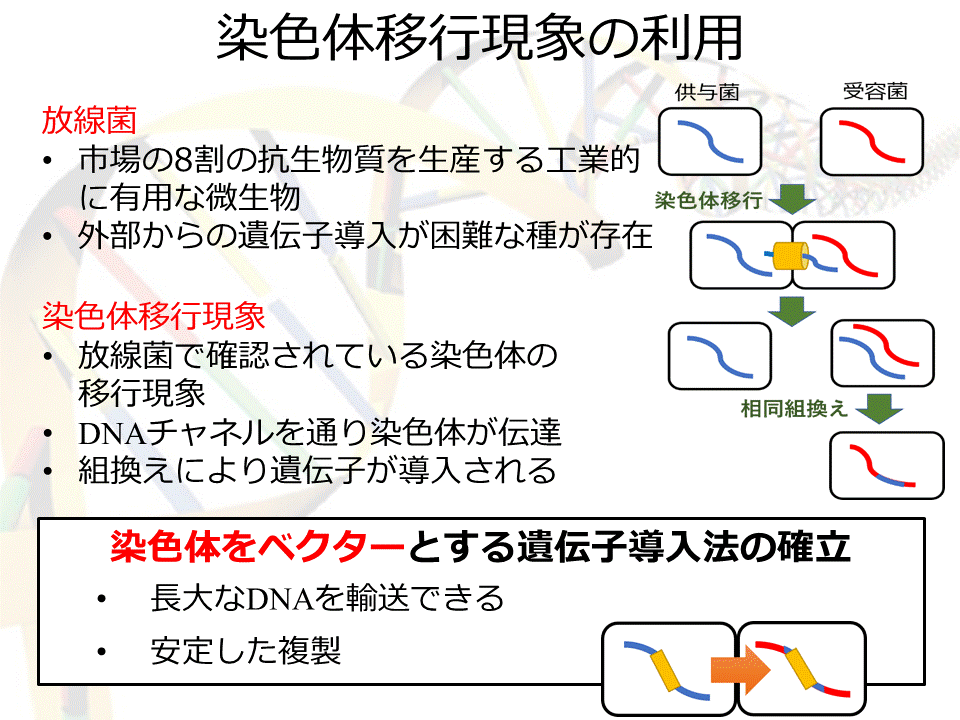
2.接合伝達に必要なoriT領域の特定
RP4というプラスミドの伝達機構を用いた接合伝達について研究しています。特にその機構のoriTと呼ばれる伝達開始起点の領域必要性を調べる研究を行っています。上記の接合伝達は、接合伝達関連タンパク質がoriT領域に結合することで開始されます。先行研究及び、当研究室で行った研究結果から、必要なoriT領域は伝達先の菌によって異なることが示唆されています。今現在はこの差が生じる原因の解明を目的として研究を行っています。
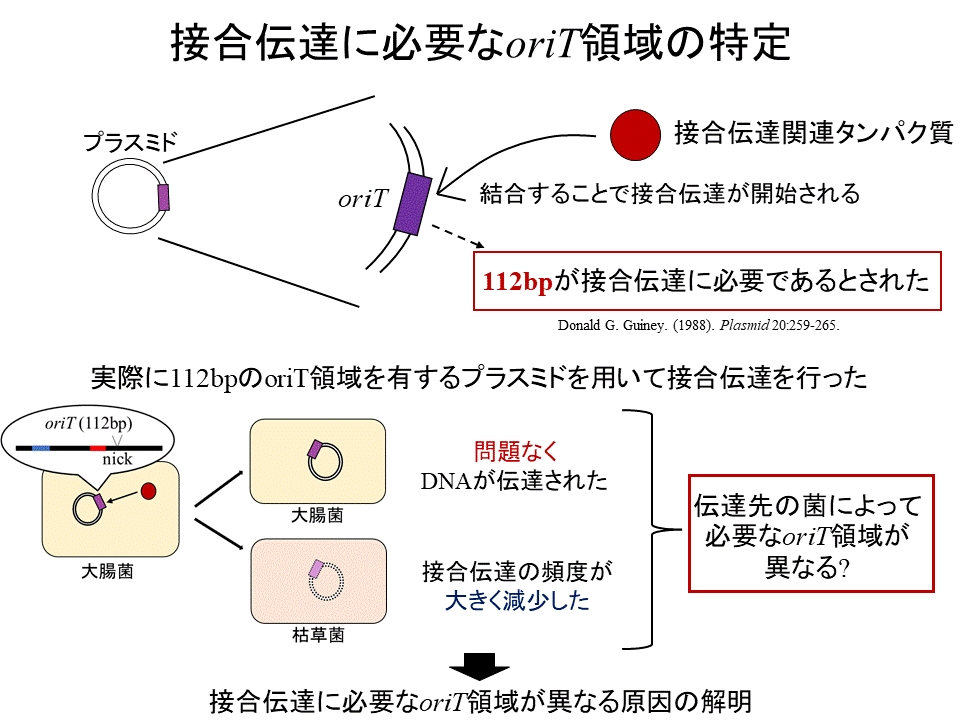
3.RP4の接合伝達機構を用いた好アルカリ菌への遺伝子導入
無性生物である細菌は、遺伝子水平伝播と呼ばれる、同時間軸での遺伝子の取り込みによって遺伝的多様性を獲得してきました。遺伝子水平伝播の主な1つである接合伝達は、細菌同士の接触により発生する、DNAの伝達現象です。
本研究では接合伝達を、遺伝子導入ツールとして利用しています。特に、広い種への伝達が報告されているRP4プラスミドの持つ接合伝達機構を用いて、大腸菌から好アルカリ菌への接合伝達による遺伝子導入を試みています。
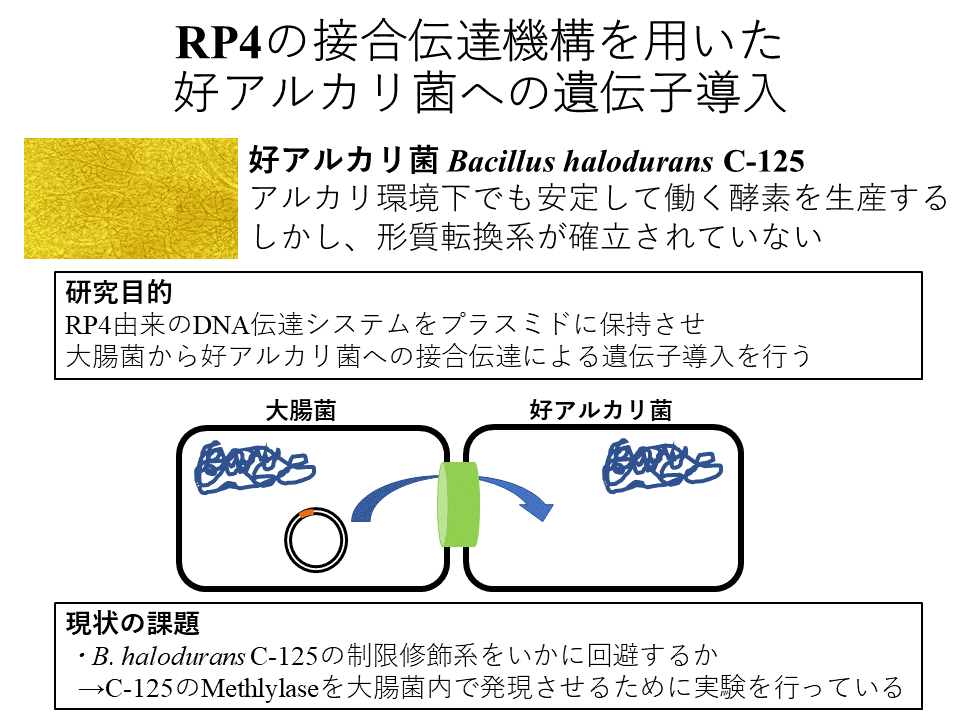
4.細胞内pHモニタリングシステムの開発
生体プロセスにおいて重要なパラメータである細胞内pHに注目し、細胞内でのpH変化を生きた状態のままリアルタイムに測定できる系の確立を目的としています。
目的達成のため、遺伝子導入により細菌内で蛍光タンパク質を発現させ、蛍光パターンの時間的変化を観測しながら、pHと生命現象の関係性について研究をしています。
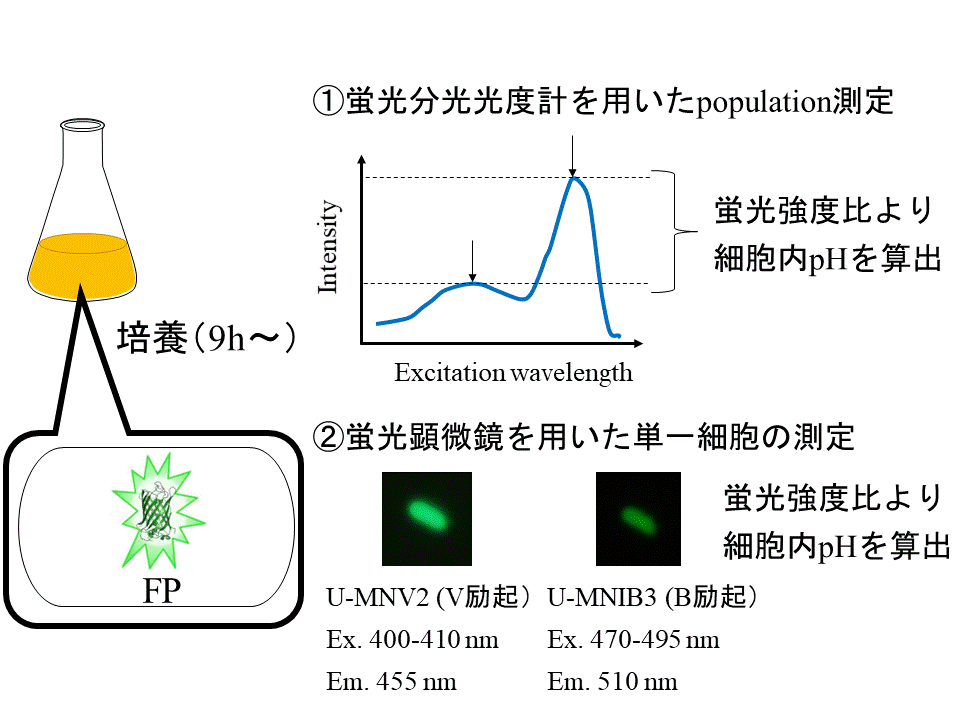
5.大腸菌細胞内pH調節機構の解明
生物には細胞内の環境を一定に保つ機能をもっており、これを恒常性と呼びます。恒常性は様々な部分で機能しており、特にpHの恒常性は代謝などの細胞内反応に影響しているため、非常に重要な機能になっています。しかし、実験でよく用いられる大腸菌でさえも細菌細胞内のpH調節機構は未だに明らかになっていない状況です。そのため、pHの調節に関わっていると考えられているNa+とK+に着目し、細胞内外のイオン環境を変化させて大腸菌細胞内pHの時間的変化を測定し、解明を行っています。
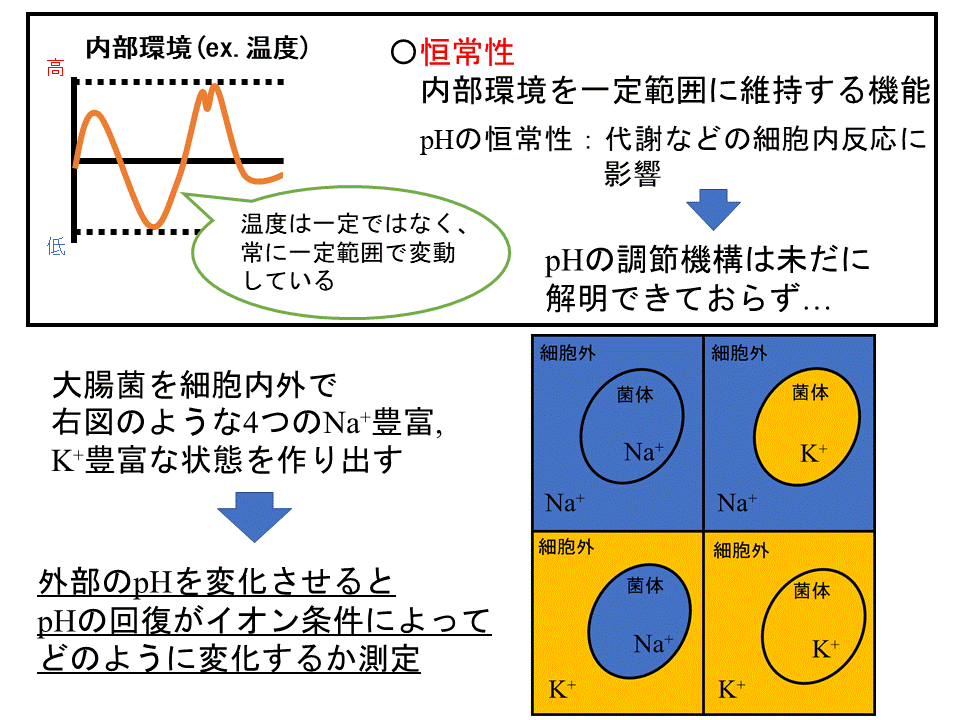
6.大腸菌細胞内pH調節遺伝子群の探索
大腸菌細胞内pH調節機構解明へのもう一つのアプローチとして、Keio collection及びColony-live systemを用いて研究を進めています。大腸菌全遺伝子の単一遺伝子欠失株(4288株)をハイスループットな菌体生育測定システムで観察し、大腸菌の細胞内pH調節に関わる遺伝子群の特定を目指しています。この研究から遺伝的相互作用(Gene intraction)など生物が持つ頑健性(ロバスト性)の解明に近づけると考えています。
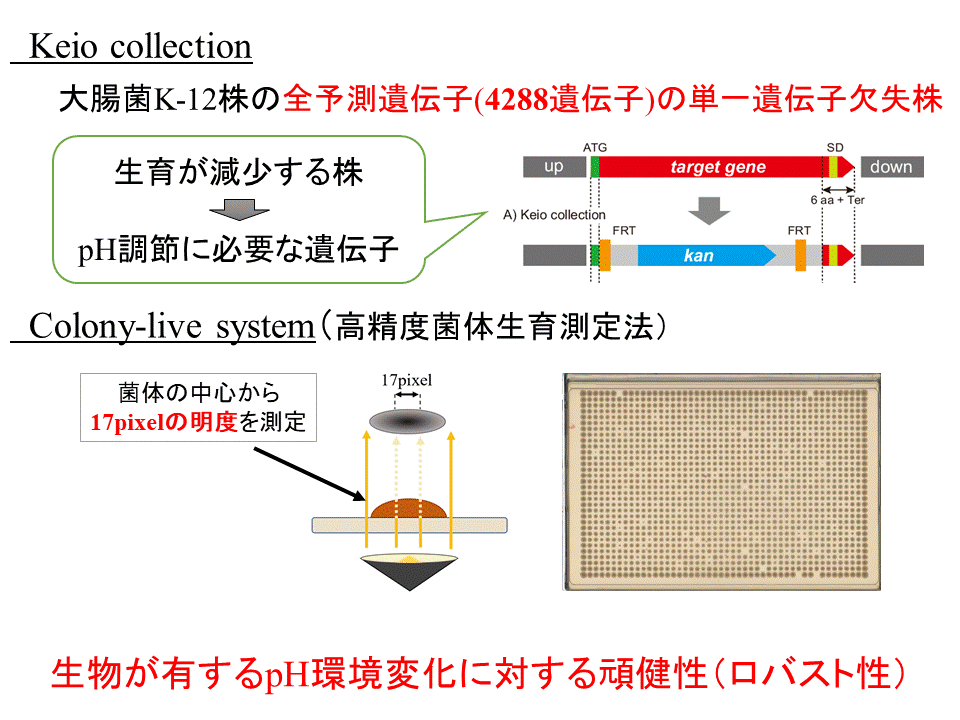
7.Colony-Liveの多種菌への適用
細菌の増殖は一般的に誘導期や対数増殖期などのいくつかの過程に分けられ、その特性は種ごとに大きく異なります。細菌を対象とした実験では増殖特性を把握しておくことが必須になります。Colony-Liveシステムは大腸菌をベースとして開発された網羅的な増殖測定システムですが、これを放線菌や枯草菌、好アルカリ菌といった様々な菌種へ適用して測定を行っています。また、細菌のコロニー形成にも注目し、細菌のコロニーとしてのかたちを捉える研究をしています。
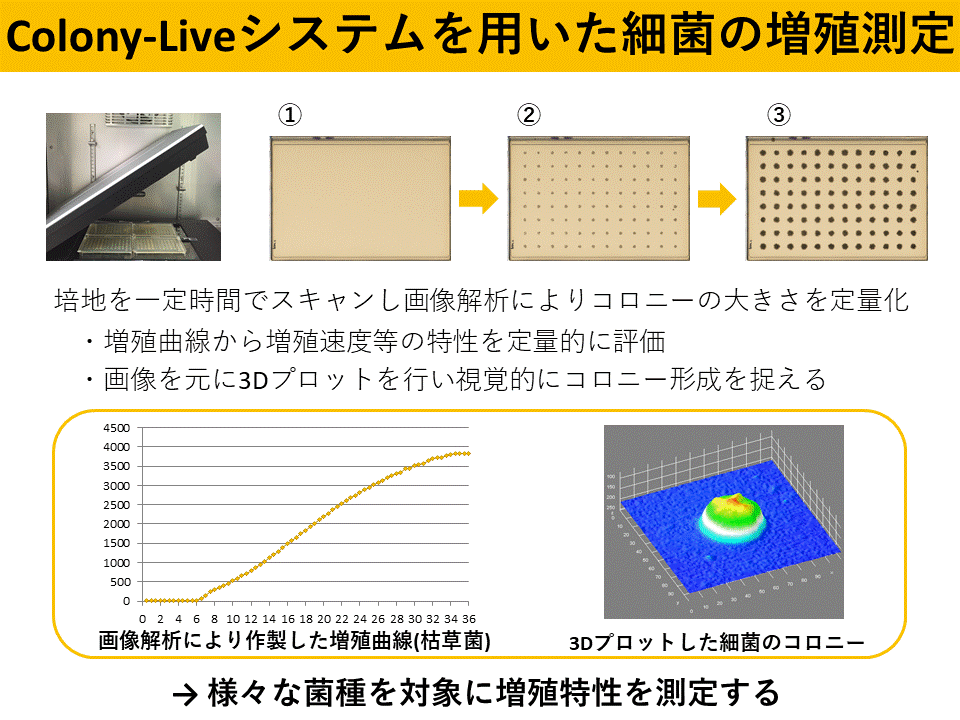
8.研究タイトル
ここに文章が入ります。
9.ラボで生きていくために必要なもの
コミュニケーション能力、知識欲、基礎的な分子生物学・遺伝学・生化学・微生物学の知識。道具としての英語、そして何よりも熱意。
10.おまけ
研究室内での流行は、"競い合い、落とし合い、けなし合い"です。こう書くと、とんでもない研究室のようですが、実は研究室内は非常に仲が良く、多くの構成員が健康的な心理的距離を保っているゆえの結果です。生命科学研究は見かけ上派手ですが、良い結果、すなわち新しい知見を得ようとすれば、無灯籠で月の無い夜道を歩くがごとく、寝る間も惜しんで研究に没頭しても実験失敗や解釈不能なデータに悩まされます。そんなときでも笑いに変えるエネルギーと精神的な健康さを如実に示す流行です。もっとも研究費を持ってくる方としては、あまり頻度が多いとちょっと泣けてしまいますが・・・本当に・・・。