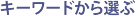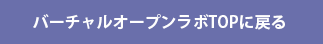- HOME
- バーチャルオープンラボ
- 耐震設計のその先へ、次世代の鉄筋コンクリート構造
耐震設計のその先へ、次世代の鉄筋コンクリート構造

2016年の熊本地震での被害調査事例(倒壊はしていないので法律上は問題がないが…)

大地震時の損傷を抑制する技術開発に関する構造実験例
大地震に対する日本の耐震設計基準は、倒壊や崩壊を防ぎあくまでも人命を確保することが目標とされています。しかし、東日本大震災や熊本地震などでは、倒壊や崩壊はしなかったものの損傷によって建物が継続使用できなくなり、多くの方々が生活困窮者となってしまいました。こうした地震災害の教訓に対して、諏訪田研究室では、RC造建築物を対象に大地震に対して損傷を抑制する構造技術や設計法に関する研究を実施しています。
研究から広がる未来
大地震が発生した際の建築物に求められる耐震性能を研究することは、“非日常”を扱うことですが、世界有数の地震多発国である日本においては実はかなり身近なことです。職業としても重要ですが、自分自身、家族、恋人、友達が大地震で被害を受けた時のことを想像してみると研究の重要性を実感するはずです。
卒業後の未来像
建設会社や設計事務所などで、構造設計や耐震改修などの専門家として活躍してほしいですが、直接構造に携わらない仕事に就いたとしても、建築物に求められる耐震性能の重要性を常に意識してほしいと願っています。さらに、日本と同様、地震が多発する開発途上国への技術支援活動や教育・研究活動にも積極的に参画してほしいです。