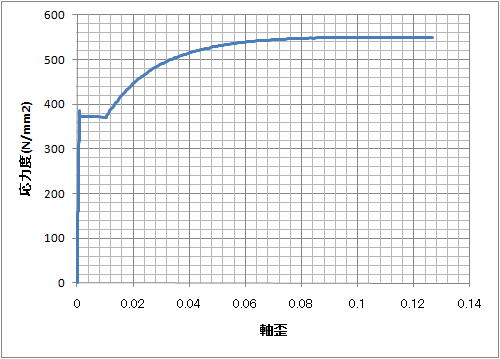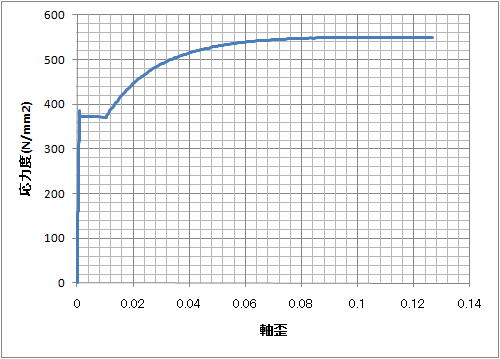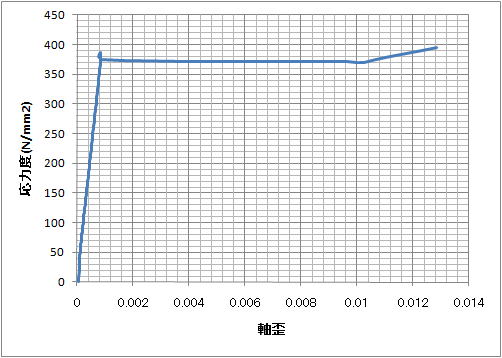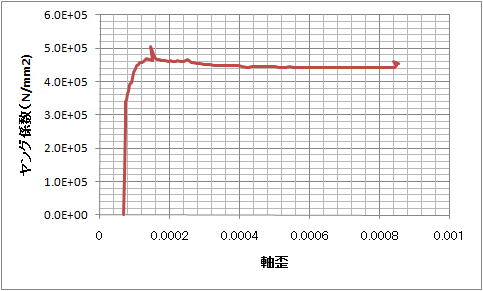鋼材引張試験
目的:異なる2種類の鋼材を用いて引張試験を行い,力学的特性の違いを確認する。
使用材料
鋼材:SD295A,SD345(SD:異形鉄筋,数値:降伏点の下限値)
試験体形状:10号試験片(10号試験片ミルシート)
試験機:200t万能試験機
実験準備
- 試験片の形状計測
- 試験片への歪みゲージの貼り付け
- 実験計画の策定
- 降伏点耐力,最大耐力の予測
- 荷重速度の設定(教科書P86)
計測項目
- 降伏点荷重(上降伏点荷重,下降伏点荷重)
- 最大荷重
- 伸び,絞り(破断後の計測)(教科書P87,88)
考察
- 降伏応力度,最大応力度,ヤング係数,伸びの規格値と実験値との比較検討
- 鋼材の種類による実験結果の相違に対する検討
試験体の準備
- 試験片の平行部に標点距離50mmおよびこれを2等分する標点をケガキする。
- 試験片の直径および各標点間距離をノギスで計測する。
- ケガキ線を入れた位置から90度の両面の標点間中央部を紙ヤスリで研磨し,アセトンを含ませた脱脂綿でよく洗浄した後,用意した歪みゲージを貼付する。
ひずみゲージ貼り付け要領
- ゲージの位置決めをおこない,テープでリード線部分を固定する。
- ゲージに瞬間接着剤を塗布し,試験片に押し当てる。
- ビニールをゲージにかぶせ,指でゲージ内の接着剤を一方向に押しだし,すぐにゲージ面を指で押さえる。
- 約1分ほど指で押さえた後,ビニールテープをはがす。
実験計画書
- 目的:試験体に対する加力方法や試験体の荷重を測定するロードセルのレンジを指定する
- 必要事項
- 実験予測値
- 加力計画:所定の単位断面積あたりの荷重速度(N/mm2/sec)にしたがって試験ができるように荷重速度(N/sec)をあらかじめ計算しておく。
- 注意事項
- 実験計画書も評価の対象にする。したがって,各自,決められた期日までに実験計画書を提出すること。
- 加力は提出された実験計画書をもとに実施する。
鋼材引張試験のレポートについて
必要項目
- 実験の目的
- 実験方法(試験体,計測計画,加力計画)
- 実験に用いる試験体の鋼種の種類,特徴
- 試験体の寸法測定方法とその結果(実測値)
- けがき,ポンチの付けた位置(実測値)
- ゲージの張り付け位置
- 加力方法,加力速度
- 使用した試験機の規格
- 実験結果の記載必要事項
- 応力度-歪み曲線(ひずみが正しく測定できないと判断した領域のデータは削除して描くこと)
- 荷重と歪みのデータはexcelのファイルで渡します。歪みは,実歪みに106をかけた値になっています。これを「マイクロストレイン」といいます。したがって,データ解析する際は,歪みの値を106で割ってください。
- 降伏点耐力,降伏応力度(降伏点)
- 最大耐力,最大応力度(引張強さ)
- ヤング係数
- 伸び
- 絞り
- 考察
- 降伏応力度,最大応力度,ヤング係数(2.05×105N/mm2),伸びの規格値(ミルシートの値)と実験値との比較検討
- 鋼材の種類による実験結果(降伏応力度,最大応力度,ヤング係数)の相違に対する検討
- その他
- 単位はSI系とする.
- 計算過程がわかるように記述する.
- 感想などは不要
実験データファイルの取り扱い
実験の後,お渡しするexcelファイルのデータの取り扱い方法です。
元のデータ
A:日時,B:経過時間,C:荷重(ton),D:歪ゲージ1の歪,E:歪ゲージ2の歪
注意点
- C列の荷重はtonで計測されるため,応力度を計算する際にはNへ変換すること。
- D,E列の値は,ひずみに106をかけた値になっている。単位はμストレインをいう。実歪みは,この値を106で割ること。
- 最初は荷重がかからないため,荷重の値が極端に小さいか,負の値を取っている。該当する部分のデータ(A〜E列)は,範囲を各自判断して削除する。
- 4行は説明のために追加した。もとのデータには無い。
データ整理のために各自追加するデータ
F:軸歪(D,Eの平均値を106で割る)
G:応力度(C列/断面積,SI単位へ変換する)
H:ヤング係数(G列/F列)
| 1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
| 2 |
|
|
CH.000 |
CH.001 |
CH.002 |
|
|
|
| 3 |
DATE & TIME |
Time(Sec.) |
CH000 |
CH001 |
CH002 |
|
|
|
| 4 |
|
|
荷重(ton) |
歪(με) |
歪(με) |
軸歪(ε) |
応力度(N/mm2) |
ヤング係数(N/mm2) |
| 5 |
2009/05/05 22:17:15 |
32.347 |
0.0012 |
131.4286 |
246.6667 |
6.57149E-05 |
0.096393443 |
1466.843024 |
| 6 |
2009/05/05 22:17:15 |
32.697 |
0.1028 |
137.1429 |
256.1905 |
6.86229E-05 |
8.257704918 |
120334.625 |
| 7 |
2009/05/05 22:17:16 |
33.048 |
0.2496 |
142.8571 |
264.7619 |
7.15534E-05 |
20.04983607 |
280208.2092 |
| 8 |
2009/05/05 22:17:16 |
33.398 |
0.3092 |
145.7143 |
272.381 |
7.30118E-05 |
24.83737705 |
340183.2862 |
| これ以降,データは続く |
レポートには以下の3種類の図を掲載する。
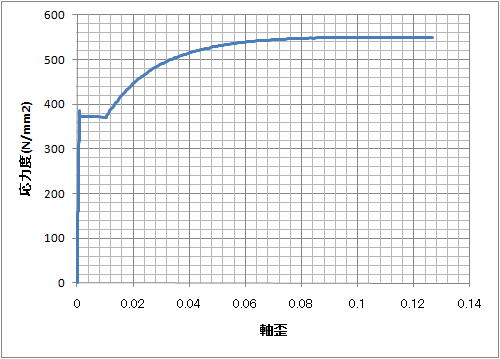
図1 応力と軸歪の関係
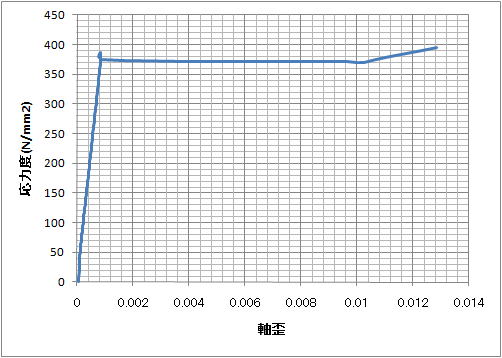
図2 応力と軸歪の関係(部分の拡大)
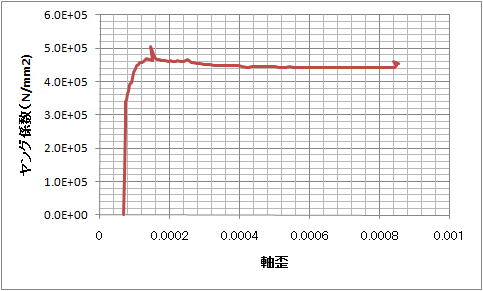
図3 ヤング係数
値が安定している範囲(軸歪が0.0005〜0.0008位の間)の平均値を採用する。