湛水土壌中直播方式と従来の湛水直播方式の比較
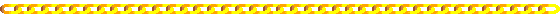
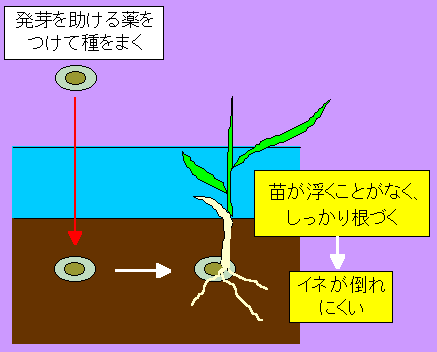
湛水土壌中直播方式
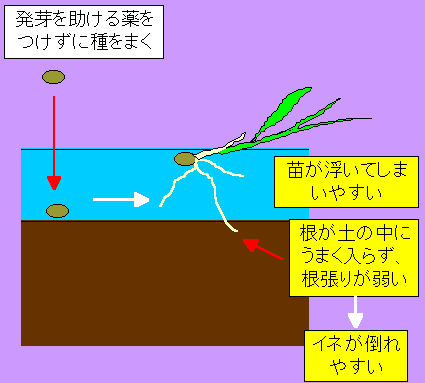
湛水直播方式(従来のやり方)
種が発芽して芽や根を伸ばす時、種や苗が水に浮いてしまって流されたり
することがあります。
苗が水に浮いてしまうと、根が土の中にうまく入っていかなくなり、苗の生長が悪くなったり、根の張りが弱くなって、倒れやすい稲になってしまいます。
完全に浮いてしまった苗はやがて枯れてしまいます。
苗が浮かないようにするために、発芽して苗が生長しはじめる頃(苗が浮きはじめる頃)に排水して、根をしっかり土の中に伸ばさせるようにすることが必要になります(この作業を「芽干し」と言います)。
ですが、この「芽干し」のために排水すると、苗がスズメに食われたり(水が溜めてあるとスズメは苗を食べられません)、水の保温効果がなくなってしまいます。
 スズメとカモは嫌われもの
スズメとカモは嫌われもの
必ずしも直播栽培に限りませんが、スズメとカモは苗(正確には、種の中身、つまりお米の部分です)を食う害鳥です。
場合によっては、まいた種がことごとく食べられてしまうこともあるので、「鳥と人間の共存」は生易しいものではありません。
東京ではカルガモが毎年人気を集めていますが、水田地帯では厄介ものなのです。
害鳥とか厄介ものという表現は、あくまでも農業の立場からいえば、ということですので、悪しからず。
●スズメは水に弱い
田んぼに溜めた水が深さ5cm程度以上あれば、水の中に入って苗を食うことはしません。
でも、水が浅くなったり、排水してしまうと一斉に食いにやってきます。
●カモは水に強い
強いというより大好き。だって、水鳥なんですから。水が溜まっていて、おいしい餌(お米)がある田んぼにやってくるのは無理もない。カモが厄介なのは、スズメよりも体が大きいので、田んぼの中を泳ぎまわられるだけで、苗を食わなくても、苗がなぎ倒されたりしてしまうこと、割に夜の間に「食事」をすることが多い夜行性のようで、人間にとっては追い払うのが大変。
※私は鳥の専門家ではないので、不適切な表現があるかもしれないことはお断りしておきます。
水を溜めなきゃ、スズメに食われ、水を溜めればカモに食われ、
ってことになるわけで、自然との戦いは厳しいです。
カモがあまりいないために、カモの害が問題にならない地域もあります。
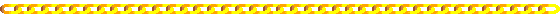
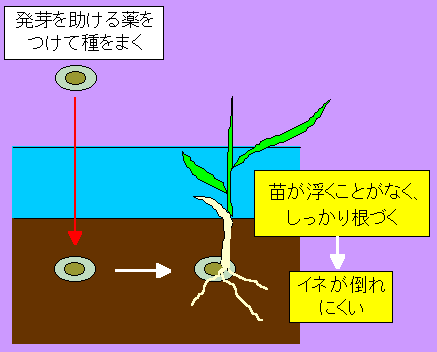
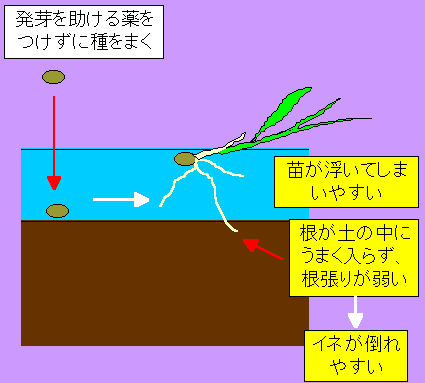
 スズメとカモは嫌われもの
スズメとカモは嫌われもの